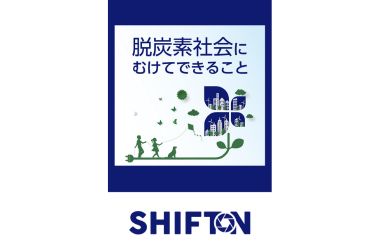溶解パルプ

溶解パルプとは?その特徴と重要性
溶解パルプ(Dissolving Pulp)は、木材やコットンリンターなどの植物繊維から、主成分であるセルロースを非常に高い純度で分離・精製した特殊な化学パルプです。一般的な紙を作るための製紙用パルプとは異なり、化学的な処理を施して様々な製品に加工されることから「化学用パルプ」とも呼ばれます。
その最大の特徴は、極めて高いセルロース純度にあります。通常、α-セルロースと呼ばれる、水酸化ナトリウム溶液に溶けない高純度のセルロースの含有率が90%以上、用途によっては98~99%に達するものもあります。これは、製紙用パルプに含まれるリグニン(木材の細胞を固める成分)やヘミセルロース(セルロース以外の多糖類)を製造工程で徹底的に除去しているためです。
この高い純度と均質性により、溶解パルプは化学薬品に均一に溶解・反応しやすく、後続の化学プロセスを経て、元のパルプとは全く異なる性質を持つ多様な素材へと生まれ変わります。衣料用繊維のレーヨンや、透明なフィルムであるセロファン、さらには食品添加物や医薬品、液晶フィルムに至るまで、私たちの生活に欠かせない多くの製品の基礎原料として、溶解パルプは重要な役割を担っています。
溶解用パルプとは何ですか?
「溶解用パルプ」は、「溶解パルプ」と同義で使われる言葉です。この名称は、溶解パルプが化学薬品に溶解させて利用されることに由来します。
具体的には、ビスコース法によるレーヨン製造では、溶解パルプを水酸化ナトリウム溶液と二硫化炭素で処理して、粘性のある液体(ビスコース)に変えます。この「溶解」プロセスが、製品を形作るための重要な第一歩となります。
このように、単に繊維を水に分散させて紙を作る製紙用パルプとは異なり、化学的に「溶解」または反応させて別の物質に変換することを前提としている点が、溶解(用)パルプの本質的な特徴を示しています。そのため、純度だけでなく、反応性や粘度といった化学的な性質も厳しく管理されています。
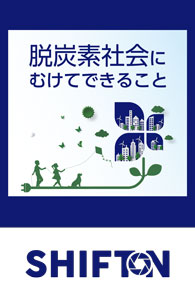
背景から実例まで網羅した
脱炭素社会への必見バイブル
- なぜ脱炭素が必要か
- 脱炭素・製品製造から加工
- クローズドリサイクル
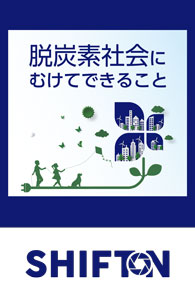
DPとはパルプの何ですか?
DPとは、重合度(Degree of Polymerization)の略称です。これは、パルプの主成分であるセルロース分子が、どれだけ長く鎖状に繋がっているかを示す指標です。セルロースは、ブドウ糖(グルコース)が多数結合してできた高分子化合物であり、DPはその鎖の中にグルコース単位が平均していくつ含まれているかを表します。
例えば、DPが1000であれば、平均して1000個のグルコース単位が繋がって1本のセルロース分子を構成していることを意味します。
溶解パルプにおいて、DPは最終製品の品質や特性を左右する非常に重要な因子です。用途によって最適なDPは異なり、製造工程で精密にコントロールされます。
- レーヨン(ビスコースレーヨン): 比較的低いDP(例:300~500程度)が求められます。DPが高すぎるとビスコース溶液の粘度が高くなりすぎ、紡糸が困難になるためです。
- セルロースアセテート(タバコフィルター、液晶フィルムなど): レーヨンよりも高いDP(例:1000~1500程度、用途により変動)が必要です。高いDPは、アセテート繊維やフィルムの強度、耐久性に寄与します。
- 高強度レーヨンや特殊用途: さらに高いDPが要求される場合もあります。
溶解パルプの製造では、原料の種類や蒸解、漂白の条件を調整することで、目的のDPを持つパルプを作り分けています。DPは、パルプの粘度測定によって間接的に評価されることが一般的です。
セルロースとパルプの違いは何ですか?
セルロースとパルプは密接に関連していますが、意味するところは異なります。
- セルロース (Cellulose):
- 地球上で最も豊富に存在する天然の高分子化合物です。
- 植物の細胞壁の主成分であり、植物の骨格を形成しています。
- 化学的には、多数のβ-グルコース分子が直鎖状に結合(β-1,4グリコシド結合)した多糖類です。
- 水に溶けにくく、高い強度を持つ繊維状の物質です。
- 綿(コットン)はほぼ純粋なセルロース(約90%以上)です。
- パルプ (Pulp):
- 木材や竹、麻、コットンリンターといった植物原料から、主にセルロース繊維を分離・抽出したものを指します。
- 製造方法によって、セルロース以外の成分(リグニン、ヘミセルロースなど)を含む度合いが異なります。
- 製紙用パルプは、紙の強度や不透明性を保つために、ある程度のヘミセルロースやリグニンを含むことがあります。
- 溶解パルプは、前述の通り、セルロースの純度を極限まで高めた(リグニンやヘミセルロースを大幅に除去した)パルプです。
簡単に言えば、セルロースは「物質名」であり、パルプは「セルロースを主成分とする工業原料(繊維の集合体)」と考えることができます。溶解パルプは、パルプの中でも特に「高純度なセルロース繊維の集合体」と言えるでしょう。
溶解パルプの製造方法と用途
溶解パルプは、その高い純度を実現するために、特殊な製造プロセスを経て生産されます。また、その用途は多岐にわたり、私たちの生活の様々な場面で活用されています。ここでは、溶解パルプの製造方法と主な用途について、関連するパルプの種類にも触れながら解説します。
溶解パルプ 製造方法
溶解パルプの製造は、原料となる植物繊維からセルロース以外の成分(リグニン、ヘミセルロース)を効率的に除去し、目的の純度とDP(重合度)を持つセルロースを得ることを目的とします。主な原料としては、広葉樹(ユーカリ、ブナなど)、針葉樹(マツ、モミなど)、そして綿花から綿繊維を採取した後に種に残る短い繊維であるコットンリンターが用いられます。
代表的な製造方法には以下のものがあります。
- 前加水分解クラフト法 (Pre-hydrolysis Kraft Process):
- 現在、溶解パルプ製造の主流となっている方法です。
- 通常のクラフトパルプ製造工程(後述)の前に、「前加水分解(Pre-hydrolysis)」という工程を追加します。
- 前加水分解では、木材チップを高温の熱水や希薄な酸で処理し、ヘミセルロースを選択的に分解・除去します。
- その後、クラフト蒸解(アルカリ蒸解)でリグニンを効率的に除去します。
- この方法により、α-セルロース含有率が95%以上といった高純度の溶解パルプを安定して製造できます。薬品回収システムが確立されているクラフト法をベースにしているため、経済性にも優れています。
- 酸性亜硫酸塩法 (Acid Sulfite Process) / サルファイト法:
- 古くから溶解パルプの製造に用いられてきた方法です。
- 亜硫酸または亜硫酸水素塩を主成分とする酸性の薬品(蒸解液)で木材チップを蒸解します。
- この方法は、ヘミセルロースの除去が比較的容易で、漂白しやすいという利点があります。特にレーヨン用途に適したパルプが得られます。
- しかし、クラフト法に比べてパルプの収率がやや低く、薬品回収システムの効率や適用できる樹種に制限がある、廃液処理の環境負荷が大きいといった課題もあります。近年では採用例が減少傾向にありますが、特定の用途向けには依然として重要な製法です。
これらの蒸解工程の後には、多段漂白工程が続きます。ここで、残留リグニンやその他の不純物をさらに除去し、パルプの白色度を高めます。環境負荷低減のため、近年ではECF(Elemental Chlorine Free:無塩素漂白)やTCF(Totally Chlorine Free:完全無塩素漂白)といった漂白技術が主流となっています。最終的に、シート状に抄き上げられ、乾燥させて製品となります。製造全工程を通じて、α-セルロース含有率、DP(粘度)、白色度、灰分(無機不純物)、樹脂分などが厳しく管理され、用途に応じた品質の溶解パルプが供給されます。
クラフトパルプとは
クラフトパルプ(Kraft Pulp, KP)は、世界で最も多く生産されている化学パルプです。ドイツ語の「Kraft(力、強度)」に由来するように、繊維が強靭であることが最大の特徴です。
製造には、水酸化ナトリウム(苛性ソーダ)と硫化ナトリウムを主成分とする強アルカリ性の薬品(白液と呼ばれる)を用い、木材チップを高温高圧(約160~170℃)で蒸解します。この処理により、木材中のリグニンが効率的に分解・除去され、セルロース繊維が取り出されます。
主な特徴:
- 高い強度: 包装用紙袋(セメント袋、米袋など)、段ボールライナーなど、強度が必要な紙製品に広く使われます。
- 薬品回収システムの確立: 蒸解に使用した薬品(黒液)を燃焼させて回収・再利用するシステムが効率的で、環境負荷とコストを低減できます。
- 幅広い原料適用性: 針葉樹、広葉樹を問わず、多くの樹種から製造可能です。
- 未漂白品は茶褐色: リグニンが完全には除去されないため、未漂白クラフトパルプ(UKP)は茶色がかっています。漂白したものは漂白クラフトパルプ(BKP)と呼ばれ、印刷用紙や衛生用紙などに使われます。
溶解パルプの製造法の一つである「前加水分解クラフト法」は、このクラフトパルプの製造技術をベースにしています。
クラフトパルプ 製造工程
クラフトパルプの一般的な製造工程は以下の通りです。溶解パルプ(前加水分解クラフト法)との比較のために示します。
- 原料受入・チップ化: 丸太を受け入れ、樹皮を剥ぎ(剥皮)、チップ化(細かく砕く)します。
- 蒸解 (Cooking/Digesting): チップを蒸解釜に入れ、白液(水酸化ナトリウム+硫化ナトリウム)と共に高温高圧(例: 170℃, 約2時間)で蒸煮します。リグニンが薬品に溶け出し、セルロース繊維が分離します。
- 洗浄 (Washing): 蒸解後のパルプ(黒液を含む)を洗浄し、薬品(黒液)とパルプ繊維を分離します。回収された黒液は薬品回収ボイラーで燃焼され、薬品とエネルギーが回収されます。
- 選別 (Screening): 未蒸解の木片や異物をスクリーンで除去します。
- (酸素脱リグニン - Oxygen Delignification, オプション): 漂白工程の負荷を低減するために、アルカリ条件下で酸素を用いて残留リグニンの一部を除去する工程。
- 漂白 (Bleaching): (BKPの場合)塩素系(二酸化塩素など)や酸素系の漂白剤を用いて多段階で漂白し、白色度を高めます。ECFやTCFが主流。
- 精選 (Cleaning): 細かいゴミなどを除去します。
- シート化・乾燥: パルプを水に分散させ、抄紙機に似た機械で脱水・シート化し、乾燥させて製品(シート状パルプやベール)にします。
前加水分解クラフト法では、上記の工程の前に「前加水分解」工程が加わります。ここでヘミセルロースを除去しておくことで、後続のクラフト蒸解と漂白を経て、高純度の溶解パルプを得ることができます。
サルファイトパルプ
サルファイトパルプ(Sulfite Pulp)は、亜硫酸または亜硫酸水素塩(例: 亜硫酸カルシウム、亜硫酸マグネシウム、亜硫酸ナトリウムなど)を含む酸性(または中性、アルカリ性の場合もある)の蒸解液で木材チップを蒸解して製造される化学パルプです。クラフト法が発見される以前から存在した古い製法です。
主な特徴:
- 比較的純粋なセルロース: クラフトパルプよりもヘミセルロースの除去が容易で、比較的純度の高いセルロースが得られます。
- 漂白しやすい: 残留リグニンが少なく、漂白しやすい特性があります。
- 繊維強度は劣る: 一般的に、クラフトパルプに比べて繊維強度は劣ります。
- 用途: かつては製紙用としても広く使われましたが、現在は溶解パルプ(特にレーヨン用)、特殊紙(グラシン紙、トレーシングペーパーなど)、食品添加物(CMCの前駆体)などの製造に主に用いられます。
溶解パルプ製造においては、酸性亜硫酸塩法は、特にレーヨン用途に適した、反応性の高いパルプを製造する方法として利用されてきました。しかし、前述の通り、薬品回収や環境負荷の課題から、新規の設備投資は前加水分解クラフト法が中心となっています。それでも、特定の品質要求を満たすために、サルファイト法による溶解パルプも依然として生産されています。
溶解パルプ 用途
高純度なセルロースである溶解パルプは、化学的な加工を経て、多種多様な製品に生まれ変わります。主な用途を以下に示します。
- 再生セルロース繊維:
- レーヨン (Rayon) / ビスコース (Viscose): 溶解パルプの最大の用途であり、世界で年間約600万トン以上が生産されています。溶解パルプをアルカリ処理し、二硫化炭素と反応させてビスコースという粘性のある液体を作り、細い孔から酸性浴中に押し出して繊維状に再生します。
- 衣料品: シルクのような光沢と滑らかな肌触りを持ち、吸湿性に優れるため、婦人服(ブラウス、ドレス)、紳士服の裏地、和装用途などに広く使われます。
- 不織布: 衛生材料(ウェットティッシュ、マスク)、医療用ガーゼなど。
- リヨセル (Lyocell) / 精製セルロース繊維: 比較的新しい製造法(NMMO法)で作られる再生セルロース繊維。有機溶剤(N-メチルモルホリン-N-オキシド)で溶解パルプを直接溶かし紡糸するため、ビスコース法に比べて環境負荷が低いとされています。テンセル™ (Tencel™)などのブランド名で知られます。強度が高く、ソフトな風合いを持ち、衣料品や寝具などに使われます。
- キュプラ (Cuprammonium Rayon) / ベンベルグ™ (Bemberg™): 主にコットンリンター由来の溶解パルプを、銅アンモニア溶液(シュバイツァー試薬)に溶解して紡糸します。非常に細くしなやかな繊維で、吸放湿性に優れ、静電気が起きにくい特徴があります。高級スーツやコートの裏地として有名です。
- セロファン (Cellophane):
- レーヨンと同様にビスコース法で作られますが、繊維状ではなくフィルム状に再生したものです。透明で光沢があり、ガスバリア性は低いですが、防湿性を持たせることができます。かつては包装材として広く使われましたが、近年はプラスチックフィルムに代替されています。食品包装(お菓子、乾物など)や工業用テープの基材などに利用されます。
- セルロース誘導体 (Cellulose Derivatives): 溶解パルプのセルロース分子にある水酸基(-OH)を化学的に修飾(エステル化、エーテル化など)して得られる高分子材料です。元のセルロースとは異なる性質を持ち、多様な機能を発揮します。
- セルロースアセテート (Cellulose Acetate):
- タバコフィルター: 最大の用途。
- 液晶ディスプレイ用フィルム (TACフィルム): 偏光板の保護フィルムとして不可欠な素材。
- プラスチック: 眼鏡フレーム、工具の柄、フィルム、繊維(アセテート繊維)。
- カルボキシメチルセルロース (Carboxymethyl Cellulose, CMC): 水溶性のセルロースエーテル。
- 食品添加物: 増粘剤、安定剤、保水剤として、アイスクリーム、ソース、麺類などに使用。
- 工業用途: 歯磨き粉、洗剤、接着剤、製紙、土木建材、医薬品(錠剤の結合剤など)に幅広く利用。
- ニトロセルロース (Nitrocellulose) / 硝化綿:
- 塗料(ラッカー)、インキ、接着剤、火薬(無煙火薬)、セルロイド(歴史的プラスチック)。
- その他:
- エチルセルロース (EC): 医薬品コーティング、インキ、接着剤。
- ヒドロキシプロピルセルロース (HPC): 医薬品(結合剤、コーティング剤)、食品添加物、化粧品。
- メチルセルロース (MC): 建材(セメント混和剤)、食品添加物、医薬品。
- セルロースアセテート (Cellulose Acetate):
このように、溶解パルプは単一の素材でありながら、その後の化学プロセスによって全く異なる機能を持つ様々な製品へと姿を変え、現代社会の基盤を支える重要な工業原料となっています。
クラフトパルプ 用途
比較のために、クラフトパルプの主な用途も見てみましょう。その高い強度特性が活かされています。
- 包装用紙:
- 重袋(じゅうたい): セメント、飼料、肥料、化学薬品などを入れるための強度のある紙袋。未漂白クラフトパルプ(UKP)が主。
- 一般紙袋: 買い物袋、角底袋など。漂白(BKP)または未漂白(UKP)。
- 段ボール原紙:
- ライナー: 段ボールの表裏に使われる平らな紙。強度が必要。UKPが多い。
- 中芯原紙: 波状の部分。古紙パルプも多く使われるが、強度を出すためにUKPを配合することも。
- 印刷・情報用紙:
- 上質紙、コピー用紙、書籍用紙など: 漂白クラフトパルプ(BKP)が主原料の一つ。
- 衛生用紙:
- ティッシュペーパー、トイレットペーパー、ペーパータオルなど: 柔らかさが求められるため、BKPの中でも特に広葉樹クラフトパルプ(LBKP)などが使われることが多い。
このように、クラフトパルプは主に物理的な強度や紙としての機能が求められる用途に使われます。一方で、溶解パルプは化学原料としての純度や反応性が重視され、化学変換を経て全く異なる製品になる、という点で明確な違いがあります。
溶解パルプまとめ
- 溶解パルプは、α-セルロース含有率が90%以上に精製された特殊な化学パルプです。
- 化学薬品に溶解・反応させて様々な製品に加工されるため、「化学用パルプ」とも呼ばれます。
- 製造方法としては、クラフト法をベースとした前加水分解クラフト法が主流であり、古くからの酸性亜硫酸塩法も用いられます。
- パルプ中のセルロース分子の長さを示すDP(重合度)が品質の重要指標であり、用途に応じてコントロールされます。
- 主な用途は、衣料品などに使われるレーヨン、包装用フィルムのセロファン、そしてタバコフィルターや液晶フィルム、食品添加物などになるセルロース誘導体(セルロースアセテート、CMCなど)です。
- 強度を活かして包装材などに使われるクラフトパルプとは異なり、溶解パルプは化学原料としての役割を担っています。
関連資料はこちら
関連記事はこちら
紙のトータルソリューション(SHIFT ON paper)について
SHIFT ON paperとは
媒体としての紙の提供から、製品のコーディネートや環境対応対策まで、紙にまつわるあらゆる課題を解決します。

SHIFT ONについて、
もっと詳しく知りたい方へ
SHIFT ONのソリューションに
関するお問い合わせや、
資料のダウンロードはこちらで承ります。
持続可能な社会や事業に向けた行動変容に対して意識を「シフト」させるための取り組みを提案します。
紙製品に関する意外と知らない用語が詰まってます!
ぜひお役立ち用語集、ご活用ください。