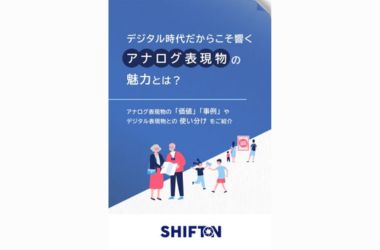針葉樹パルプ

針葉樹とは:まっすぐに伸びる森のシンボル
「針葉樹(しんようじゅ)」とは、細くて尖った針のような形や、鱗のような形の葉を持つ樹木の総称です。
スギ、ヒノキ、マツ、モミなどがその代表的な種類です。
これらの樹木は、一年を通して葉をつける「常緑樹」が多く、冬でも緑を保つことから、日本の風景において重要な要素となっています。
ただし、カラマツのように秋に葉を落とす「落葉樹」の針葉樹も一部存在します。
針葉樹は、主に冷温帯から亜寒帯にかけて広く分布しており、広葉樹と比較すると比較的単純な種類の森を形成することが多いです。
日本の森林面積約2,500万ヘクタールのうち、約4割にあたる約1,000万ヘクタールが人工林であり、その約9割がスギやヒノキなどの針葉樹林です(林野庁「森林・林業白書」令和4年度版より)。
これは、建築用材などとして利用するために人が植林したものが多いためです。

針葉樹の主な特徴
針葉樹は、広葉樹とは異なるいくつかの特徴を持っています。
- 葉の形: 最も顕著な特徴は、細長い針のような形や、ヒノキのように鱗が重なったような形の葉です。
表面積が小さいため、乾燥や寒さに強い構造になっています。 - 花の形: 花は小さく目立たず、一般的に風によって花粉が運ばれる風媒花です。
スギ花粉症の原因となるスギの雄花などが知られています。 - 果実: 一般的に「球果(きゅうか)」と呼ばれる、いわゆるマツボックリのような形をしています。
球果の鱗片の間に種子が入っています。 - 材の構造: 材(木材)の構造は比較的単純で、主に仮道管と呼ばれる細胞で構成されています。
このため、木目がまっすぐで均一な傾向があります。
広葉樹材に比べて一般的に軽くて柔らかいものが多いですが、種類によっては硬いものもあります。 - 成長速度: 一般的に広葉樹に比べて成長が速い傾向があります。
特にスギやヒノキなどの人工林は、短期間で木材として利用するために品種改良や施業が行われています。 - 生態系への貢献: 針葉樹林は、広葉樹林に比べて樹種や植物の種類が少ない傾向がありますが、特定の動物や昆虫の生息場所となります。
また、水源涵養や土砂崩れの防止など、公益的機能も担っています。
代表的な針葉樹の種類
日本には多様な針葉樹が自生・植林されており、古くから私たちの生活に深く関わってきました。
代表的な針葉樹をいくつかご紹介します。
- スギ: 日本で最も多く植林されている樹種で、日本の森林面積の約18%を占めます。
成長が速く、軽くて加工しやすいため、建築材、家具材、割り箸など幅広い用途に利用されます。
花粉症の原因としても知られています。 - ヒノキ: スギに次いで多く植林されており、特に強度や耐久性に優れるため、高級建築材として寺社仏閣などに古くから用いられてきました。
独特の良い香りが特徴です。 - アカマツ・クロマツ: マツの仲間で、海岸沿いや乾燥した土地にも生育します。
材はヤニが多く、建築材や燃料として利用されます。
盆栽としても人気があります。 - カラマツ: 日本の針葉樹では珍しい落葉樹です。
成長が速く、北海道や長野県などで多く植林されています。
建築材や土木用材に利用されます。 - モミ: クリスマスツリーとしてもおなじみの樹種です。
常緑で、比較的標高の高い場所に生育します。
材は建築材や包装材に利用されます。
これらの他にも、ツガ、トドマツ、エゾマツなど、日本の気候や風土に適応した様々な針葉樹が存在し、それぞれの特性を活かして多様な形で利用されています。
針葉樹とは:産業とパルプ利用におけるその重要性
針葉樹は、木材としての利用価値が非常に高く、日本の林業において中心的な役割を担ってきました。
特に建築分野では、その加工しやすさや強度から主要な構造材として広く利用されています。
また、紙の原料となるパルプとしても、針葉樹は重要な位置を占めています。
ここでは、針葉樹が持つ産業的な価値と、広葉樹との違い、そして針葉樹パルプ(NBKP)に焦点を当てて詳しく見ていきましょう。
針葉樹と広葉樹の違い
樹木は大きく「針葉樹」と「広葉樹」に分けられますが、これらは葉の形だけでなく、材の性質や成長の仕方など、様々な点で違いがあります。
これらの違いが、それぞれの木材の用途やパルプにしたときの特性に影響を与えています。
まず葉の形を見ると、針葉樹は細くて尖った針状や鱗状の葉を持つのに対し、広葉樹は平たくて幅の広い様々な形の葉を持ちます。
花については、針葉樹は小さく目立たない風媒花が多い一方、広葉樹は小さく目立たないものから、サクラのように大きくて美しい花を咲かせるものまで多様です。
果実も異なり、針葉樹はマツボックリのような球果をつけるのに対し、広葉樹はドングリやクリ、サクランボなど多種多様な果実をつけます。
種子は、針葉樹は球果の鱗片の間にあるのに対し、広葉樹は果実の中に含まれます。
落葉性については、針葉樹はカラマツなど一部を除いて常緑樹が多いですが、広葉樹は落葉樹が多いものの常緑樹も存在します。
材の構造にも違いがあり、針葉樹材は主に仮道管で構成され比較的単純で木目がまっすぐな傾向がありますが、広葉樹材は道管が発達し構造が複雑で木目も多様です。
成長速度は一般的に針葉樹の方が速い傾向がありますが、広葉樹は一度大きくなると豊かな枝葉を茂らせます。
代表的な樹種としては、針葉樹にはスギ、ヒノキ、マツ、カラマツ、モミなどがあり、広葉樹にはブナ、ナラ、ケヤキ、サクラ、カエデ、カシなどがあります。
このように、針葉樹材は一般的に軽くて柔らかく、まっすぐな木目を持ち、加工がしやすいという特徴があります。
一方、広葉樹材は硬くて重いものが多く、複雑で多様な木目を持つ傾向があります。
針葉樹材の強度
針葉樹 強度は、広葉樹材と比較すると一般的に低いとされていますが、これはあくまで平均的な傾向です。
実際には、樹種や生育環境、材の部位によって強度は大きく異なります。
例えば、ヒノキやベイマツなどは、針葉樹の中でも強度が高く、建築物の構造材として重要な役割を果たしています。
針葉樹材の強度は、主に以下の要素で評価されます。
- 曲げ強度: 材が曲げられたときに耐えられる力。
梁などに使われる際に重要です。 - 圧縮強度: 材が圧縮されたときに耐えられる力。
柱などに使われる際に重要です。 - 引張強度: 材が引っ張られたときに耐えられる力。
- せん断強度: 材がずらされる力に耐えられる力。
接合部などで重要です。
日本の建築基準法では、使用する木材の種類や強度に応じて、建物の構造計算を行うことが定められています。
針葉樹材は、その強度特性を考慮した上で、柱や梁、筋かいなどの構造部材として広く利用されており、日本の木造建築を支えています。
例えば、一般的な木造住宅では、柱や梁にスギやヒノキの無垢材や集成材が使用されることが多いです。
針葉樹パルプ(NBKP)とは?
紙の原料となるパルプのうち、針葉樹を原料として作られたものを「針葉樹パルプ」と呼びます。
英語では「Softwood Kraft Pulp」と呼ばれ、漂白されたものは「Bleached Softwood Kraft Pulp」、略して「BSKP」または「NBKP (Needle-tree Bleached Kraft Pulp)」と呼ばれます。
針葉樹パルプ とは、針葉樹材を化学的または機械的に処理して繊維を取り出し、必要に応じて漂白したものです。
主にクラフトパルプ法という化学的な方法で製造されます。
NBKPの繊維長と特性
NBKPの最も重要な特徴は、その繊維が広葉樹パルプ(LBKP)に比べて長いことです。
- 針葉樹パルプ(NBKP)の繊維長: 平均約2.5〜3.5mm程度
- 広葉樹パルプ(LBKP)の繊維長: 平均約0.7〜1.0mm程度
この長い繊維が、紙にしたときに繊維同士がしっかりと絡み合うことで、紙の機械的な強度を高めます。
NBKPの主な特性は以下の通りです。
- 強度: 繊維が長いため、引裂強度、破裂強度、引張強度といった紙の機械的強度に優れています。
破れにくく、丈夫な紙を作るのに適しています。 - 通気性: 繊維が太く、紙の構造に隙間ができやすいため、通気性が比較的高い傾向があります。
- 嵩高性: 繊維がしっかりしているため、紙にボリューム感(嵩)を与えることができます。
これらの特性から、NBKPは強度や耐久性が求められる様々な紙製品の製造に不可欠な原料となっています。
針葉樹パルプの用途
針葉樹パルプ 用途は多岐にわたります。
その長い繊維と高い強度を活かして、主に以下のような紙製品に利用されます。
- 新聞用紙: 高速印刷に耐えうる強度と、インクの吸収性が求められる新聞用紙の主要な原料です。
- 段ボール原紙: 段ボールのライナー(表面の平らな紙)や中芯(波状の紙)の原料として、高い強度と剛性が求められます。
- 紙袋: セメント袋や肥料袋など、重いものを入れるための丈夫な紙袋に利用されます。
- クラフト紙: 包装用や封筒などに使われる、強度が高く耐久性のある紙です。
- 特殊紙: フィルター用紙や絶縁紙など、特定の機能が求められる特殊な紙にも利用されます。
- ティッシュペーパー・トイレットペーパー: 柔らかさを出すためにLBKPとブレンドされることが多いですが、強度を持たせるためにNBKPも配合されます。
日本の紙・板紙の生産量におけるNBKPの割合も高く、2022年のデータでは、パルプ消費量約1,000万トンのうち、NBKPの割合は約2割程度を占めています(日本紙パルプ連合会データより)。
LBKPとNBKPは、それぞれの特性を補い合う形でブレンドされ、多様な紙製品の製造に貢献しています。
針葉樹パルプの価格
針葉樹パルプ 価格は、世界の需給バランス、為替レート、原料となる木材の価格、エネルギーコストなど、様々な要因によって変動します。
NBKPはLBKPに比べて繊維が長く高品質であることから、一般的にLBKPよりも価格が高い傾向にあります。
パルプ価格は国際的な商品市場で取引されており、その価格変動は製紙会社の収益に大きな影響を与えます。
例えば、世界的な紙需要の変動(特にアジア市場の動向)、主要なパルプ生産国(カナダ、北欧、南米など)での供給状況の変化、あるいは輸送コストの変動などが価格に影響を与えます。
近年では、環境規制の強化や持続可能な森林経営への意識の高まりも、長期的なパルプ供給や価格形成に影響を与える要因となっています。
パルプ価格の動向は、最終的に私たちが購入する紙製品の価格にも反映される可能性があります。
針葉樹パルプとはまとめ
針葉樹パルプ(NBKP)は、針葉樹を原料とする紙の主要な原料の一つです。
その最大の特徴は、広葉樹パルプ(LBKP)に比べて繊維が長いこと(平均約2.5〜3.5mm)であり、この特性が紙に高い機械的強度(引裂強度、破裂強度、引張強度など)をもたらします。
NBKPは、新聞用紙、段ボール原紙、紙袋、クラフト紙など、強度や耐久性が求められる紙製品の製造に不可欠な原料として広く利用されています。
LBKPの短い繊維(平均約0.7〜1.0mm)が紙に平滑性や柔らかさを与えるのに対し、NBKPは紙の骨格を形成し、破れにくさを付与する役割を担います。
両者は製造する紙製品の用途や品質に応じて最適な比率でブレンドして使用されます。
NBKPの価格は国際的な需給バランスやコストによって変動し、一般的にLBKPより高価な傾向にあります。
針葉樹パルプは、私たちの日常生活に欠かせない様々な紙製品を支える重要な素材です。
関連資料はこちら
紙のトータルソリューション(SHIFT ON paper)について
SHIFT ON paperとは
媒体としての紙の提供から、製品のコーディネートや環境対応対策まで、紙にまつわるあらゆる課題を解決します。

SHIFT ONについて、
もっと詳しく知りたい方へ
SHIFT ONのソリューションに
関するお問い合わせや、
資料のダウンロードはこちらで承ります。
持続可能な社会や事業に向けた行動変容に対して意識を「シフト」させるための取り組みを提案します。
紙製品に関する意外と知らない用語が詰まってます!
ぜひお役立ち用語集、ご活用ください。