生物多様性クレジット

生物多様性クレジットの基本理解:定義と仕組み
生物多様性クレジットとは?その定義と目的
「生物多様性クレジット」とは、自然の回復、保全、持続可能な管理活動から得られる、測定可能なプラスの生物多様性の成果の単位を表します。これは、生物多様性の損失を食い止め、回復させるための活動に資金を供給することを主な目的とする経済的手段です。
世界経済フォーラムによると、生物多様性クレジットは「生物多様性の純利益をもたらす活動に資金を提供するために使用される経済的手段」と定義されています。これは、自然にプラスとなる企業活動をサポートし、長期的な自然保護と回復に資金を提供することを可能にする新たな市場の一つとして位置づけられています。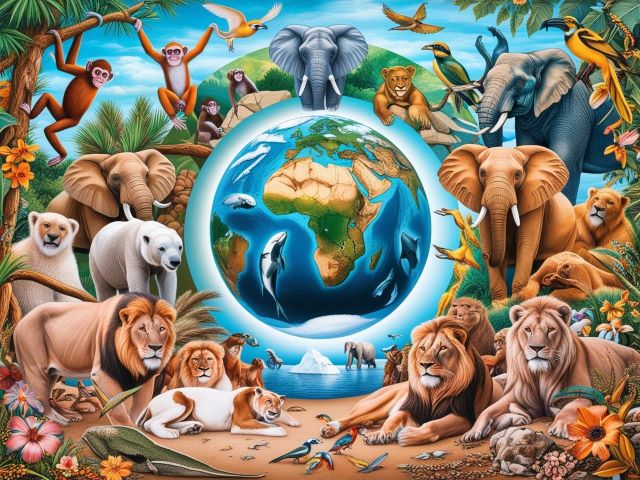
生物多様性クレジットの主な目的は以下の通りです。
- 資金調達の促進: 生物多様性保全・回復活動には多大な資金が必要です。クレジットの発行・取引を通じて、新たな資金源を確保します。
- インセンティブの提供: 生物多様性に貢献する活動を行う主体(土地所有者、地域コミュニティなど)に対して、経済的なインセンティブを提供し、活動を促進します。
- 成果の定量化と可視化: 生物多様性への貢献を測定可能な単位で示すことで、活動の成果を明確にし、関係者間の信頼性を高めます。
- ネイチャーポジティブ経済への貢献: 企業や投資家が生物多様性クレジットを購入することで、自社の事業活動における生物多様性への影響を考慮し、全体として自然にプラスとなる経済活動への転換を後押しします。
生物多様性クレジットの創出プロセスは、以下のステップで進められます。
- プロジェクトの特定と計画: 生物多様性保全・回復を目指す特定の場所や活動を特定し、詳細な計画を策定。
- ベースライン設定: プロジェクト実施前の生物多様性の状態を測定し、ベースラインを設定。
- 活動の実施: 計画に基づき、活動を実施。
- 成果の測定と検証: プラス成果を科学的に測定し、第三者検証。
- クレジットの発行: 検証された成果に基づき、特定の単位で発行。
- 取引: 発行されたクレジットを企業や個人に販売。
この仕組みを通じて、活動担い手は資金を得て、購入者は貢献を表明できます。
生物多様性オフセットとの違い
生物多様性クレジットと混同されやすい概念に「生物多様性オフセット」があります。両者は自然への貢献に関わる経済的メカニズムですが、その目的と機能には重要な違いがあります。
生物多様性オフセットは、人間の活動による生物多様性へのマイナスの影響を相殺・補償する目的を持ちます。これは、開発行為を行う場所での損失を、別の場所でのプラスの影響(回復や保全)で埋め合わせる考え方で、「ミティゲーション・ヒエラルキー」の最終手段です。
一方、生物多様性クレジットは、特定の負の影響相殺を前提とせず、生物多様性に肯定的な成果をもたらす活動に資金を提供し、成果を単位化・取引することに焦点を当てています。企業が事業活動とは直接関連しない場所でも、積極的に生物多様性向上に貢献するための手段として期待されます。
関連項目:生物多様性オフセットとは
IAPB(国際諮問パネル)による市場健全化への取り組み
生物多様性クレジット市場が持続的に発展し、その信頼性を確保するためには、明確なルールと高い基準が不可欠です。この課題に対応するため、「生物多様性クレジットに関する国際諮問パネル(IAPB: International Advisory Panel on Biodiversity Credits)」が設立されました。
IAPBは、信頼性の高い生物多様性クレジット市場の発展を目指し、「生物多様性クレジット市場の健全性を高めるためのフレームワーク」を公表しています。これには、クレジットの質と信頼性を保証する「ハイレベル原則」と運用ガイダンスが含まれます。原則には、科学的検証に基づく成果、地域社会の権利尊重、活動の追加性・永続性、漏出回避、透明性が挙げられます。これらの原則は、クレジットが実質的な生物多様性向上に貢献し、「グリーンウォッシュ」を防ぐ基盤となります。IAPBの取り組みは、市場の国際的な信頼と普及に不可欠です。
生物多様性クレジットの現状と今後の展望
COP16で議論された生物多様性クレジット
生物多様性条約COP16(2024年10月/2025年2月再開会合)では、生物多様性クレジットが注目され、新たな資金源としての期待と、信頼性・実効性(定量評価、地域影響など)の課題が議論されました。特に「定量評価」の重要性が強調され、今後の市場ルール形成に影響を与える一歩となりました。
日本における生物多様性クレジットの現状と課題
日本でも生物多様性クレジットへの関心が高まり、環境省は関連戦略やガイドラインで推進しています。日本の課題は里地里山の担い手不足や海外資源依存です。クレジットは地域貢献の可能性を秘める一方、生物多様性に特化した仕組みは発展途上です。主な課題は評価手法確立、市場設計、普及啓発、地域性配慮、既存制度連携であり、関係者が課題克服に向け議論や実証実験を進めています。
生物多様性クレジット事例
生物多様性クレジットに関する取り組みは、国内外で始まっています。
黎明期ですが、いくつかの事例があります。
- 企業による生態系回復: 環境省の「ネイチャーポジティブ経営推進プラットフォーム」では、JFEホールディングスによる「マリンストーン®」活用での海域の底質や水質の改善、日本製鉄による「ビバリーⓇユニット」活用での海藻類生育が紹介されています。これらはクレジット化の対象となりうる活動です。
- 都市部での試み: 株式会社BIOTAは、オフィスビル緑地の微生物多様性向上を評価し「トークン」として発行する試みを進めており、都市部での新しいクレジットとしてTNFD開示での活用も期待されています。
これらの事例は、多様な形態の生物多様性クレジットが存在することを示します。重要なのは、活動が信頼性高く評価・認証され、取引されるかです。
生物多様性クレジット市場の動向と将来性
生物多様性クレジット市場は、カーボンクレジット市場より小規模ですが、生物多様性の危機認識の高まりやTNFD開示の動きと連動し、注目度が増しています。
市場動向としては、IAPBによるフレームワーク構築、多様な評価手法開発、テクノロジー活用(ブロックチェーンなど)、企業からの関心の高まりが挙げられます。
今後の展望として、生物多様性クレジット市場は、持続可能な社会実現に向けた重要な資金調達メカニズムとして成長が予想されます。市場拡大には、信頼性確保(厳格な基準、透明性)、需要創出(政策支援、啓発)、多様なプロジェクト開発、国際連携が鍵となります。
生物多様性クレジットは課題も多いですが、生物多様性危機克服とネイチャーポジティブな未来構築の強力なツールとなる可能性を秘めています。市場の健全な発展に向け、関係者間の連携と継続的な努力が求められます。
生物多様性クレジットまとめ
生物多様性クレジットは、自然回復・保全のプラス成果を単位化し、資金供給とネイチャーポジティブ実現を目指す経済メカニズムであり、オフセットとは異なり積極的な向上に焦点を当てます。
日本でも関心は高いものの、評価手法や市場設計など課題があります。国内外で事例が増え、市場は黎明期ながら発展の兆しを見せています。
市場の健全な成長は生物多様性危機対応と持続可能な社会構築に不可欠であり、今後の動向に注目し、理解・活用が重要です。
参考
- 環境省 「ネイチャーポジティブ経営推進プラットフォーム」
https://www.biodic.go.jp/biodiversity/private_participation/business/ - JFEスチール株式会社 「海域環境改善用粒度調整鉄鋼スラグ マリンストーン®」
https://www.jfe-steel.co.jp/products/slag/b07.html - 日本製鉄 建設用資材ハンドブック
https://www.nipponsteel.com/product/construction/handbook/pdf/11-22.pdf - 株式会社 BIOTA 【プレスリリース】オフィスビルの緑地を活用した生物多様性の再生を促進する「生物多様性クレジット」
https://biota.city/news/post-1493/
関連資料はこちら
関連記事はこちら
~SHIFT ONではこんなサービスがご提供可能です~
SHIFT ON greenとは
SDGsやカーボンニュートラルなど、環境対応プロジェクトの企画から実行まで包括的に支援します。
関連ページ
SHIFT ONの関連サービスについてお問い合わせ
SHIFT ON greenでは環境・機能材ソリューションをご提案いたします。
まずはお気軽にお問い合わせよりどうぞ。
SHIFT ONについて、
もっと詳しく知りたい方へ
SHIFT ONのソリューションに
関するお問い合わせや、
資料のダウンロードはこちらで承ります。
持続可能な社会や事業に向けた行動変容に対して意識を「シフト」させるための取り組みを提案します。
紙製品に関する意外と知らない用語が詰まってます!
ぜひお役立ち用語集、ご活用ください。


