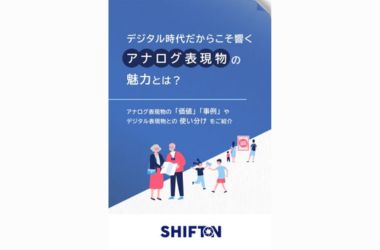黒液

製紙産業は、私たちの生活に欠かせない紙製品を供給する重要な産業です。その製造プロセス、特に化学パルプ(クラフトパルプ)の製造過程で副産物として生成される「黒液(こくえき)」は、単なる廃液ではなく、製紙工場のエネルギー自給や薬品回収において極めて重要な役割を担っています。
この記事では、製紙業における黒液とは何か、その成分、利用方法、管理における注意点、そして関連技術について詳しく解説します。
黒液とは何か?製紙工程における重要性
黒液は、主に木材からリグニンなどの不要な成分を分離し、セルロース繊維(パルプ)を取り出す「クラフトパルプ化法」という化学的な蒸解工程で発生する液体です。木材チップを水酸化ナトリウム(NaOH)と硫化ナトリウム(Na2S)を含む薬液(白液)で高温高圧下で煮込む(蒸解)と、木材中のリグニンやヘミセルロースの一部が溶解し、パルプ繊維と分離されます。この時にパルプ繊維を取り除いた後の、リグニンや薬品、木材由来の有機物が溶け込んだ黒褐色の廃液が「黒液」と呼ばれます。
この黒液は、単に廃棄されるのではなく、製紙工場内でエネルギー源および薬品回収の原料として有効活用される、非常に価値の高い物質です。
製紙業におけるクラフトパルプ法と黒液の発生
クラフトパルプ法は、強度が高く高品質なパルプを製造できるため、世界中で最も広く採用されている化学パルプの製造方法です。そのプロセスは以下のようになります。
- 木材チップ化: 原木を細かく砕き、木材チップにします。
- 蒸解: 木材チップを蒸解釜に入れ、白液(水酸化ナトリウムと硫化ナトリウムの混合液)と共に高温(約150~170℃)・高圧で数時間煮込みます。この過程で、セルロース繊維を結合しているリグニンやヘミセルロースの一部が薬品によって分解・溶解されます。
- 分離・洗浄: 蒸解後、釜から内容物を取り出し、パルプ繊維と、リグニンや薬品が溶け込んだ液体(黒液)を分離します。パルプは洗浄工程へ送られます。
- 黒液の回収: 分離された黒液は、回収工程へと送られます。発生直後の黒液(希薄黒液)は固形分濃度が15~18%程度と低いため、そのままでは燃料として効率が悪く、輸送も困難です。
この蒸解工程で木材チップ中の約半分がパルプとなり、残りの半分(主にリグニン、ヘミセルロース分解物)と使用された薬品が黒液の成分となります。つまり、1トンのパルプを生産すると、ほぼ同量の有機物が黒液中に溶け出す計算になります。
黒液の主成分とその特徴
黒液の組成は、使用する木材の種類(針葉樹か広葉樹か)、蒸解条件などによって変動しますが、主な成分は以下の通りです。
- 水: 大部分を占めます。希薄黒液では80%以上が水です。
- 有機物:
- リグニン分解物: 木材の約20~30%を占めるリグニンがアルカリによって分解されたもの。黒液の黒褐色の原因であり、主要な発熱量源です。乾燥固形分中の約30~45%を占めます。
- ヘミセルロース分解物: ヘミセルロースが分解して生じた有機酸(サッカリン酸など)やその塩。
- その他: 樹脂酸、脂肪酸など。
- 無機物:
- 蒸解で使用された薬品: 水酸化ナトリウム(NaOH)、硫化ナトリウム(Na2S)が反応して生じた炭酸ナトリウム(Na2CO3)、硫酸ナトリウム(Na2SO4)、未反応の薬品など。乾燥固形分中の約30~40%を占めます。
特徴としては、リグニン由来の構造を持つため黒褐色を呈し、アルカリ性の薬品を含むため強いアルカリ性を示します。また、有機物を豊富に含むため、乾燥・濃縮すれば燃料としての価値が高まります。リグニンはフェノール系の高分子化合物であり、その複雑な構造が燃料としてのエネルギーポテンシャルを与えています。
黒液のpHについて
黒液は、蒸解工程で使用される水酸化ナトリウムなどの強アルカリ性薬品が溶解しているため、非常に高いpH値を示します。一般的に、黒液のpHは12~13以上の強アルカリ性です。
この高いpHは、以下の点で重要です。
- 腐食性: 強アルカリ性は金属材料に対して腐食性を持つため、黒液を取り扱う設備(配管、タンク、ボイラーなど)には耐食性の高い材料(ステンレス鋼など)を使用する必要があります。
- 安全管理: 皮膚や目に付着すると化学火傷を引き起こす可能性があるため、取り扱いには保護具の着用が必須です。
- プロセスへの影響: 回収工程における化学反応(苛性化など)に影響を与えます。
黒液の利用と管理:エネルギー源としての側面と注意点
製紙工場から排出される黒液は、単なる廃棄物ではなく、資源循環と省エネルギーの観点から非常に重要な役割を果たしています。エネルギー源としての活用と、その管理における注意点を解説します。
エネルギー源としての黒液:バイオマス発電
黒液に含まれるリグニンなどの有機物は、木材由来のバイオマス資源です。これを燃料として利用することで、製紙工場はエネルギーの一部または大部分を自給することが可能です。
- 濃縮: 発生直後の希薄黒液(固形分濃度15~18%)は、多段エバポレーター(蒸発缶)を用いて水分を蒸発させ、固形分濃度を65~80%程度まで濃縮します。この濃縮黒液は粘性が高く、常温では固化するため、高温で扱われます。
- 燃焼: 濃縮された黒液は、後述する「黒液回収ボイラー」に噴霧され、高温で燃焼されます。黒液の持つ発熱量は乾燥固形分あたり約13~15 MJ/kg(メガジュール/キログラム)程度とされ、これは木質バイオマス燃料に匹敵します。
- 発電: 燃焼によって発生した熱エネルギーで高圧蒸気を生成し、タービンを回して発電します。この電力は工場内の動力として使用され、余剰分は電力会社に売電されることもあります。
日本の製紙産業におけるエネルギー消費量のうち、黒液や廃材などのバイオマスエネルギー(自家発電)で賄われる割合は高く、省エネルギーとCO2排出削減に大きく貢献しています。経済産業省のデータによると、紙・パルプ産業は産業部門の中でも特に自家発電比率が高い業種の一つであり、黒液はその中核を担っています。多くの大規模クラフトパルプ工場では、工場全体のエネルギー需要の大部分(時には100%近く)を黒液燃焼で賄っています。
黒液回収ボイラーの役割と仕組み
黒液回収ボイラー(リカバリーボイラーとも呼ばれます)は、黒液処理システムの中核をなす非常に重要な設備であり、主に以下の二つの役割を担っています。
- エネルギー回収: 濃縮黒液を燃焼させ、その熱エネルギーを回収して高圧蒸気を生成します。この蒸気は発電や工場内の他の工程(パルプ乾燥、抄紙工程など)で利用されます。
- 薬品回収: 黒液中に含まれるナトリウム(Na)や硫黄(S)といった無機薬品を回収し、再び蒸解工程で使用できる形(白液)に再生します。これにより、高価な薬品を繰り返し利用でき、環境負荷も低減できます。
回収ボイラーの基本的な仕組み:
- 噴霧・燃焼: 高温(100℃以上)に保たれた濃縮黒液が、ボイラー炉内にスプレーノズルから噴霧されます。
- 乾燥・熱分解・燃焼: 炉内の高温環境(約1000~1200℃)で、黒液中の水分が蒸発し、有機物が熱分解・燃焼します。
- スメルト生成: 燃焼により有機物が除去された後、無機成分(主に炭酸ナトリウムNa2CO3と硫化ナトリウムNa2S)は炉の底部で溶融状態の「スメルト」と呼ばれる物質になります。
- スメルト溶解: 溶融したスメルトは炉底から連続的に抜き出され、希薄白液(または水)に溶解されて「緑液」となります。
- 熱回収: 燃焼ガスはボイラーの水管群を通過する際に熱交換を行い、水を加熱して高圧蒸気を発生させます。
- 緑液処理(苛性化): 緑液はその後、石灰(酸化カルシウムCaO)と反応させる苛性化工程を経て、蒸解に使用される白液(水酸化ナトリウムNaOHと硫化ナトリウムNa2Sの溶液)として再生されます。
回収ボイラーは、製紙工場のエネルギー効率と経済性、そして環境保全(薬品リサイクル)を支える心臓部と言える設備です。
黒液の取り扱いにおける危険性
黒液は有用な資源である一方、その特性上、取り扱いにはいくつかの危険性が伴います。
- 高温: 濃縮黒液や回収ボイラー内のスメルトは非常に高温(濃縮黒液は100℃以上、スメルトは800℃以上)であり、接触すると重度の火傷を負う危険があります。
- 強アルカリ性: pHが12~13以上と高いため、皮膚や目に付着すると化学火傷を引き起こします。適切な保護具(耐薬品性手袋、保護メガネ、保護衣など)の着用が不可欠です。
- 腐食性: 高アルカリ性と、場合によっては硫黄分を含むため、設備材料に対して腐食性を示します。適切な材質選定と定期的な点検・メンテナンスが重要です。
- スメルトと水の接触爆発: 回収ボイラーにおける最大の危険の一つが、炉底に溜まった高温の溶融スメルトと水が接触した場合に起こる「スメルト・ウォーター爆発」です。これは水が急激に蒸発して体積が膨張することによる物理的な爆発で、甚大な被害を引き起こす可能性があります。ボイラーの水管からの水漏れなどが原因となりうるため、厳重な管理と監視が必要です。
- 環境汚染: 万が一、黒液が河川などに流出した場合、高いpHや有機物による水質汚濁(BOD/COD負荷)を引き起こす可能性があります。貯蔵タンクや配管からの漏洩防止対策が重要です。
これらの危険性に対処するため、製紙工場では厳格な安全管理基準に基づいた運転・保守管理が行われています。
製紙業にはなぜ多くの水が必要なのでしょうか?
製紙業、特にパルプから紙を製造する工程では、大量の水が不可欠です。その主な理由は以下の通りです。
- 原料(木材チップ)の洗浄・輸送: 汚れを除去し、工程内でチップを搬送するために水が使われます。
- パルプ化(蒸解・離解): 化学薬品を溶解させ、木材チップに浸透させ、リグニンを溶かし出すために水が必要です。また、機械パルプの場合は、木材繊維を水中で解きほぐす(離解)ためにも使われます。
- パルプの洗浄・漂白: 蒸解後のパルプから不要な薬品やリグニンを洗い流したり、漂白薬品を溶解・反応させたりするために大量の水が必要です。
- パルプの輸送・希釈: パルプ繊維を配管で輸送したり、抄紙機(紙をすく機械)にかける前に均一な濃度(通常は1%以下)に薄めたりするために水が使われます。紙の地合い(繊維の絡み合い具合)を均一にするために、極めて薄い濃度にする必要があります。
- 抄紙工程: 抄紙機のワイヤーパートで、希釈されたパルプ液から水を濾き取り、繊維を絡み合わせて紙のシートを形成します。
- 設備の洗浄・冷却: 各種装置や配管の洗浄、機械の冷却などにも水が利用されます。
- 蒸気発生: ボイラーで蒸気を発生させ、乾燥工程や発電に利用します。
このように、製紙工程のほぼ全段階で水が媒体として、あるいは洗浄・冷却用として必要不可欠です。近年の技術開発により、製紙工場では水の使用量を削減し、排水を処理して再利用する「クローズド化」が進められていますが、それでもなお大量の水を必要とする産業であることに変わりはありません。製品1トンあたりの用水使用量は、工場の設備や製造する紙の種類によって大きく異なりますが、数十トンから百トン以上に及ぶこともあります。
黒液の英語表現
黒液は、英語では一般的に "Black Liquor" と呼ばれます。これは、その見た目の色(黒色)と液体(Liquor)であることから、直訳的に表現されています。製紙業界や化学工学の分野で広く使われている専門用語です。
黒液 まとめ
黒液は、クラフトパルプ製造工程における重要な副産物であり、単なる廃液ではありません。その主な特徴と重要性をまとめます。
- 発生: 木材チップをアルカリ薬品で蒸解する際に、リグニンや薬品が溶け出して生成される黒褐色の液体。
- 成分: 水、リグニン分解物、ヘミセルロース分解物、無機薬品(ナトリウム化合物など)が主成分。
- 性質: pH 12~13以上の強アルカリ性で、腐食性がある。
- 利用: 濃縮して固形分濃度を高めた後、回収ボイラーで燃焼され、バイオマス燃料として発電や蒸気供給に利用される。製紙工場のエネルギー自給に不可欠。
- 薬品回収: 燃焼後の無機物は回収され、化学薬品(白液)として再生・再利用される。資源循環の要。
- 管理: 高温、強アルカリ性、スメルト・ウォーター爆発のリスクなど、取り扱いには厳重な安全管理が必要。
- 関連: 製紙業では多くの水が必要であり、黒液の処理・利用はその水循環システムの一部とも言える。
このように、黒液は製紙工場の持続可能な運営(エネルギー自給、薬品リサイクル、環境負荷低減)において、中心的な役割を担う重要な物質です。その適切な管理と効率的な利用は、製紙産業の競争力と環境調和を支える鍵となっています。
参考文献・出典:
●日本製紙連合会:https://www.jpa.gr.jp/
関連資料はこちら
関連記事はこちら
~SHIFT ONではこんなサービスがご提供可能です~
SHIFT ON greenとは
SDGsやカーボンニュートラルなど、環境対応プロジェクトの企画から実行まで包括的に支援します。
関連ページ
SHIFT ONの関連サービスについてお問い合わせ
SHIFT ON greenでは環境・機能材ソリューションをご提案いたします。
まずはお気軽にお問い合わせよりどうぞ。
SHIFT ONについて、
もっと詳しく知りたい方へ
SHIFT ONのソリューションに
関するお問い合わせや、
資料のダウンロードはこちらで承ります。
持続可能な社会や事業に向けた行動変容に対して意識を「シフト」させるための取り組みを提案します。
紙製品に関する意外と知らない用語が詰まってます!
ぜひお役立ち用語集、ご活用ください。