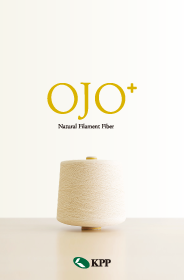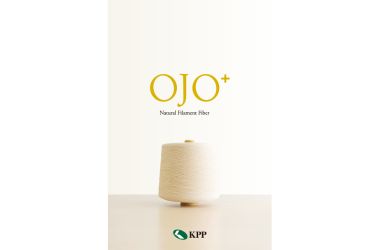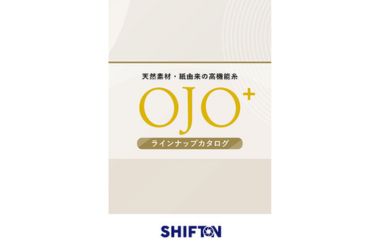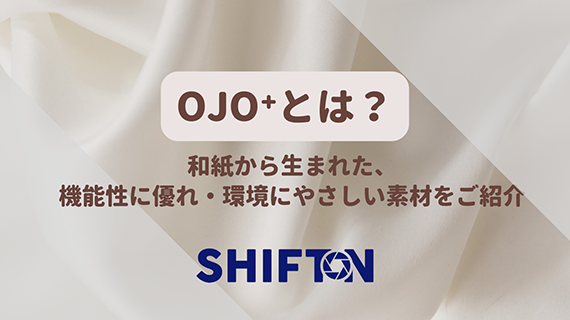抄繊糸

和紙から生まれる繊維「抄繊糸」とは?
抄繊糸は、その名の通り、「紙を抄(す)いて作る繊維」を意味します。具体的には、和紙やクラフトパルプなどの紙を細く裁断し、それを撚り(より)合わせて糸にしたものです。紙から作られた糸と聞くと、弱くて水に溶けてしまうイメージがあるかもしれませんが、抄繊糸は従来の紙の概念を覆すほどの強度と機能性を持ち合わせています。
その起源は古く、奈良時代には紙衣(かみこ)として存在し、当時の公家の衣料や武士の陣羽織などに用いられていました。特に、和紙の原料となる楮(こうぞ)や三椏(みつまた)は、繊維が長く強靭であるため、糸にしても高い耐久性を持つことが知られていました。この伝統的な知恵と技術が、現代の抄繊糸へと受け継がれているのです。
抄繊糸の読み方とその驚きの歴史
抄繊糸は、「しょうせんし」と読みます。「抄」は「紙を抄く」という意味を持つ漢字であり、「繊」は「細かい、ほそい」という意味の「繊細」にも使われるように、「繊維」を表します。
その歴史は深く、一説には平安時代の『延喜式(えんぎしき)』という書物にも「紙衣」という記述が見られ、紙で作られた衣服が既に存在していたことがわかっています。江戸時代には、和紙の技術が発展し、紙糸を用いた衣服や生活用品が庶民の間でも広まりました。特に、軽くて通気性に優れた紙糸の特性は、高温多湿な日本の気候に適しており、重宝されていました。
現代では、これらの伝統技術に加えて、最新の紡績技術や加工技術が加わることで、より快適で機能的な抄繊糸が開発されています。例えば、特定の加工を施すことで、初期の硬さを軽減し、肌触りをより柔らかくする工夫がなされています。
和紙から糸を作る抄繊糸の原理とは
抄繊糸の製造原理は、一般的な綿やポリエステルなどの繊維とは大きく異なります。綿が綿花から繊維を取り出し、それを紡いで糸にするのに対し、抄繊糸は「紙を抄く」という工程が非常に重要になります。
- 原料の準備: 和紙の原料となるマニラ麻や楮(こうぞ)などの植物繊維を、伝統的な製法で漉いて抄繊糸の元となる原紙を製造します。この薄くても丈夫な紙が、後の糸の強度を決定づけます。
- 細断: 完成した紙を、専用のカッターで非常に細いテープ状にカットします。その幅はわずか1mmから6mm程度と極めて細く、この工程の精度が最終的な糸の品質に直結します。
- 撚り合わせ: 細いテープ状の紙を、高速で撚り合わせて糸状にします。この「撚り」の工程が、紙の耐久性を格段に高める鍵となります。撚り合わせることで、紙の繊維が絡み合い、引っ張り強度や摩耗に対する抵抗力が生まれます。
- 加工: 必要に応じて、撚り合わせた糸に撥水加工や防臭加工を施し、衣料品や雑貨に最適な状態に仕上げます。
この独自の製法によって、抄繊糸は綿糸に比べて約1.5倍の強度を持つことが、ある実験データで示されています。さらに、紙の持つ天然の多孔質構造が、優れた吸湿・速乾性や軽量性、そして特有のシャリ感を生み出しています。
驚くべき「抄繊糸」の特徴と和紙服の魅力
抄繊糸は、単なる紙の糸というだけでなく、その優れた機能性から多くの魅力を持っています。特に、和紙服という形で衣料品に利用されることで、その真価が発揮されます。以下に、抄繊糸の主な特徴を挙げます。
- 驚くほどの軽さ: 原料が紙であるため、繊維自体が非常に軽量です。一般的なコットンTシャツと比較して、抄繊糸を使用したTシャツは、約20%以上軽いというデータもあります。この軽さは、夏場の衣服やインナーとして抜群の快適さを提供します。
- 高い吸湿・速乾性: 紙の繊維は中が空洞になっている「中空構造」を持っており、これが水分を素早く吸収し、同時に放出します。そのため、汗をかいても肌にまとわりつかず、常にサラッとした肌触りを保ちます。ある試験では、コットン素材が水分を完全に乾燥させるのに数時間かかるのに対し、抄繊糸は半分以下の時間で乾燥したという結果も出ています。
- 優れた消臭・抗菌性: 紙の繊維が持つ天然の多孔質構造は、気になるニオイ成分を吸着する効果が期待できます。特定の研究機関の調査では、アンモニアに対する消臭効果が約90%以上あることが確認されており、衣服だけでなく、靴下などにも適した素材と言えます。
- 肌に優しいシャリ感: 抄繊糸特有のシャリ感は、肌への接触面積を減らし、風が通り抜けるような涼しさを感じさせます。これは、高温多湿な日本の夏を快適に過ごす上で大きなメリットとなります。また、洗濯を繰り返すことで、徐々に柔らかく肌に馴染んでいくのも魅力の一つです。
抄繊糸のデメリットとその解決策
抄繊糸は多くのメリットを持つ一方で、いくつかのデメリットも存在します。これらの特性を理解し、適切なケアを行うことで、長く愛用することができます。
- 価格: 製造に手間がかかり、熟練した技術を要するため、一般的な綿や化学繊維の製品に比べて高価になりがちです。しかし、その機能性やサステナブルな価値を考慮すると、納得できる価格とも言えます。
- シワになりやすい: 天然繊維であるため、特に洗濯後や乾燥時にシワになりやすい傾向があります。これは、アイロンをかけるか、乾燥時に軽く手で叩いてシワを伸ばすことで解決できます。
- 初期の硬さ: 新品の状態では、素材特有のハリ感や硬さを感じる場合があります。しかし、これは数回の着用や洗濯を繰り返すことで、徐々に柔らかくなり、肌に馴染んでいきます。
抄繊糸の正しい洗濯方法とケア
抄繊糸の衣料品を長持ちさせるためには、正しい洗濯とケアが不可欠です。
- 手洗いまたは洗濯ネットを使用: 型崩れやシワを防ぐため、基本的には手洗いが推奨されます。洗濯機を使用する場合は、必ず「弱水流モード」や「ドライコース」を選び、大きめの洗濯ネットに入れて洗うようにしましょう。
- 中性洗剤を使用: 漂白剤や蛍光剤の入っていない、衣料用の中性洗剤を使用してください。
- 脱水は短めに: 強すぎる脱水はシワの原因になります。脱水時間を短めに設定するか、手で軽く絞る程度に留めましょう。
- 陰干しが基本: 直射日光は繊維を傷める可能性があるため、風通しの良い日陰で干すのがベストです。乾燥機は縮みやシワの原因となるため、使用は避けてください。
これらの方法で適切にケアすれば、抄繊糸の特性を損なうことなく、長くその快適さを楽しむことができます。
SHIFT ONが取り扱う紙の糸OJO⁺のご紹介
OJO⁺は、抄繊糸のDNAを受け継ぎながら、独自の特許技術でその魅力を現代に蘇らせています。再生可能な木材パルプを主原料とし、独自の製法で加工することで、紙本来の清涼感や軽やかさを保ちつつ、従来の抄繊糸では難しかった高い強度と耐久性を実現。洗っても破れにくい、画期的な繊維へと進化しました。
肌にさらりと心地よい独特の風合いと、地球に優しいサステナブルな素材であることも大きな特徴です。ファッションやインテリア、生活雑貨など、幅広い分野でその可能性が花開いており、私たちの暮らしに自然と調和した新しい価値と快適さをもたらします。
抄繊糸まとめ
抄繊糸は、和紙という日本の伝統的な素材から生まれた、次世代の機能性繊維です。その読み方は「しょうせんし」。軽量で吸湿速乾性に優れ、消臭効果も期待できるという、現代のライフスタイルにぴったりの特徴を持っています。価格や初期の硬さといったデメリットも存在しますが、それらを上回る快適性と、サステナブルな素材としての価値は非常に高いと言えます。
今後、和紙服やその他の製品で抄繊糸を目にする機会は増えていくでしょう。このユニークな素材の魅力を理解し、ぜひあなたの生活にも取り入れてみてください。
参考
- 株式会社キュアテックス「抄繊糸について」 https://www.curetex.jp/what-is-curetex
- 一般社団法人 日本繊維産業連盟「サステナブルな素材開発の現状」 https://www.jtf.or.jp/
関連資料はこちら
関連記事はこちら
~SHIFT ONではこんなサービスがご提供可能です~
SHIFT ON greenとは
SDGsやカーボンニュートラルなど、環境対応プロジェクトの企画から実行まで包括的に支援します。
関連ページ
SHIFT ONの関連サービスについてお問い合わせ
SHIFT ON greenでは環境・機能材ソリューションをご提案いたします。
まずはお気軽にお問い合わせよりどうぞ。
SHIFT ONについて、
もっと詳しく知りたい方へ
SHIFT ONのソリューションに
関するお問い合わせや、
資料のダウンロードはこちらで承ります。
持続可能な社会や事業に向けた行動変容に対して意識を「シフト」させるための取り組みを提案します。
紙製品に関する意外と知らない用語が詰まってます!
ぜひお役立ち用語集、ご活用ください。