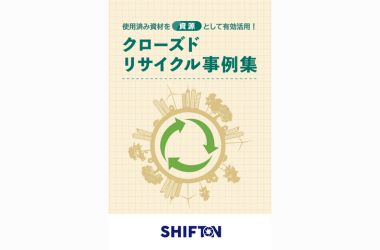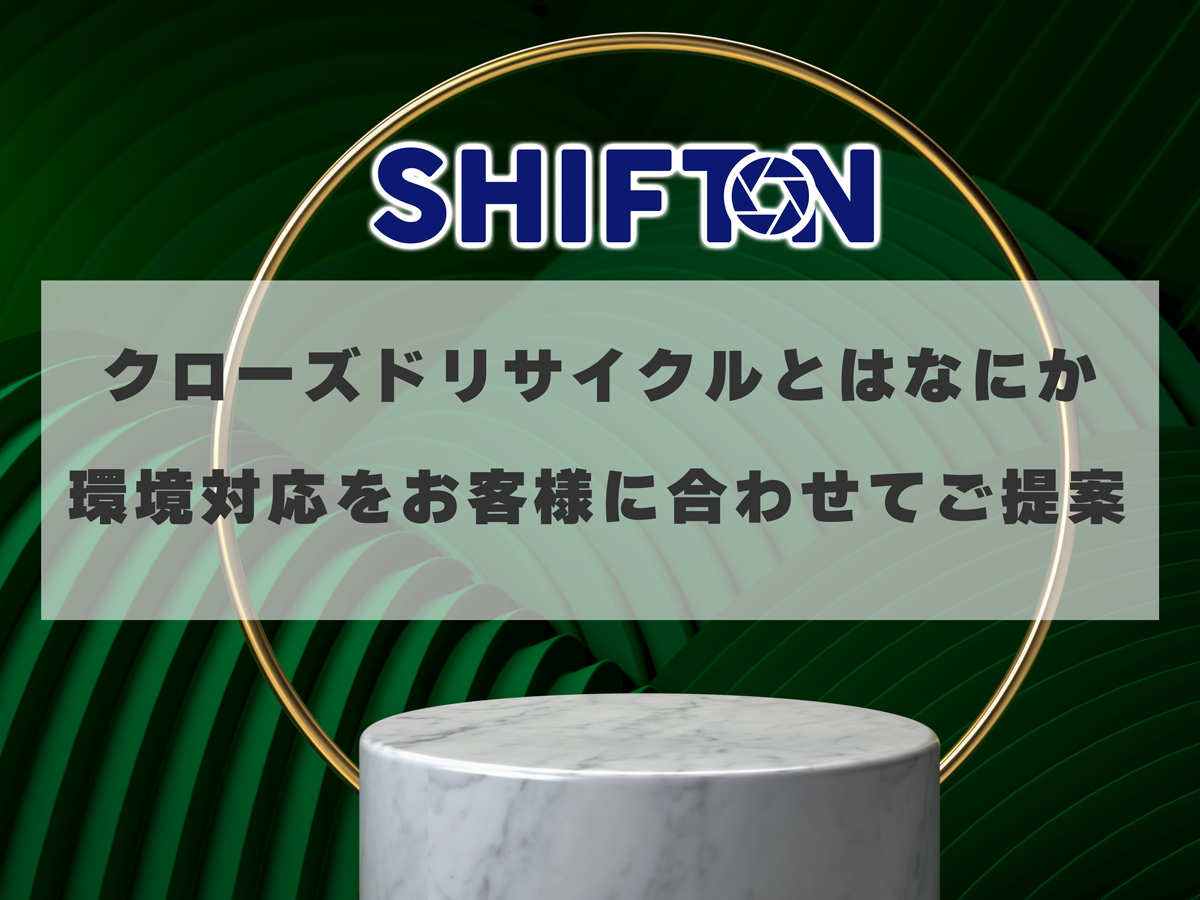サーキュラーデザイン

近年、地球環境問題や資源枯渇への懸念が高まる中、「サーキュラーエコノミー(循環経済)」への移行が世界的な潮流となっています。
その実現に不可欠な考え方として注目されているのが「サーキュラーデザイン」です。
このサーキュラーデザインについて、基本的な概念から具体的な事例、関連用語との違いまで、分かりやすく解説していきます。
サーキュラーデザインとは何か?
サーキュラーデザインとは、製品、サービス、そしてそれらを取り巻くシステムを、設計段階から意図的に廃棄物と汚染を排除し、製品と素材の価値を可能な限り高く維持しながら循環させ、さらに自然システムを再生することを目指すデザインアプローチです。
従来のリニアエコノミー(直線経済)は、「採取(Take)→製造(Make)→廃棄(Dispose)」という一方向の流れでした。
しかし、このモデルでは大量の資源が消費され、大量の廃棄物を生み出し、環境負荷を増大させてきました。
事実、世界では年間約21.2億トンもの廃棄物が発生しており、これは東京ドーム約1,700個分に相当します。
このままでは、2050年には廃棄物量が年間34億トンに達すると予測されています。(出典:世界銀行 2018年レポート ※数値は記事作成時点の調査による)
サーキュラーデザインは、このリニアエコノミーから脱却し、資源が循環し続ける「サーキュラーエコノミー」を実現するための重要な鍵となります。
製品ライフサイクルのあらゆる段階、つまり原材料の調達、設計、製造、流通、使用、回収、再利用、リサイクルといったプロセス全体を通じて、資源効率を最大化し、環境負荷を最小限に抑えることを目指します。
欧州委員会の報告によれば、製品の環境負荷の最大80%は設計段階で決定づけられるとされており、デザインこそがサーキュラーエコノミー実現のための最も重要な介入点となるのです。
エレン・マッカーサー財団は、サーキュラーエコノミーへの移行により、2030年までに欧州だけでも年間最大6,000億ユーロ(約84兆円)の経済効果が期待できると試算しています。
サーキュラーデザインは、環境保全だけでなく、新たなビジネスチャンスや経済成長にも貢献する可能性を秘めているのです。
サーキュラーデザインの基本原則(サーキュラーデザインプラクティスとは何か?)
サーキュラーデザインを実践する上で、エレン・マッカーサー財団が提唱する3つの基本原則があります。
これらは「サーキュラーデザインプラクティス」の根幹をなす考え方です。
-
廃棄物・汚染を出さない設計 (Eliminate waste and pollution by design):
製品やサービス、プロセスを設計する段階から、廃棄物や汚染が決して発生しないようにすることを求めます。
材料選択、製造プロセス、流通、使用、使用後までライフサイクル全体を考慮し、リサイクルや再利用を前提とした設計(例: 分解しやすい構造、有害物質の回避)を行います。
これは従来の廃棄物管理(Waste Management)から、資源管理(Resource Management)への転換であり、環境負荷を未然に防ぐ最も効果的なアプローチです。 -
製品と素材を(最高の価値で)循環させる (Circulate products and materials (at their highest value)):
一度使用された製品、部品、素材を価値ある資源として捉え、経済システムの中で可能な限り長く、そして高い価値を保ったまま循環させ続けることを目指します。
具体的には、メンテナンス、修理、再利用(リユース)、改修(リファービッシュ)、再製造(リマニュファクチャリング)、そして最終手段としてのリサイクルといった多様な戦略があります。
特に、メンテナンスやリユースといった加工度の低い「内側のループ」を優先することが、資源の価値を高く維持する上で重要とされています。
これを実現するには、製品を当初から耐久性があり、修理しやすく、分解しやすいように設計することが不可欠です。 -
自然を再生する (Regenerate nature):
単に環境への悪影響を最小限に抑える(less bad)だけでなく、積極的に自然システムを回復・再生させる(more good)ことを目指す、より野心的な目標です。
再生可能な資源(バイオマスなど)を持続可能な方法で利用し、使用後は安全に自然界へ還す(例:堆肥化)、あるいは土壌の肥沃度向上や生物多様性の保全に貢献するような活動を通じて、人間の経済活動が自然の再生プロセスを助ける仕組みを構築します。
資源を循環させることで、新たな資源採取の必要性を減らし、自然が本来持つ回復力を支援します。
これらの3原則は相互に関連し補完し合っています。
サーキュラーデザインの実践においては、これらの原則を統合的に考え、製品やビジネスの特性に応じて最適な循環モデルを構築していく必要があります。
サステナブルデザインとエコデザインの違いは何ですか?
サーキュラーデザインとしばしば比較される言葉に、「サステナブルデザイン」と「エコデザイン」があります。
これらは関連性が高いものの、焦点が異なります。
-
エコデザイン (Eco-design): 「環境配慮設計」とも訳され、主に製品のライフサイクルにおける環境負荷の低減に焦点を当てたデザインです。
省エネルギー、省資源、リサイクル可能性の向上、有害物質の削減などが具体的な目標となります。
リニアエコノミーの枠組みの中で、環境への影響を「より少なくする(Less bad)」ことを目指すアプローチと言えます。 -
サステナブルデザイン (Sustainable Design): エコデザインよりも広範な概念で、環境(Environment)、社会(Society)、経済(Economy)の3つの側面を統合的に考慮し、持続可能な社会の実現を目指すデザインです。
環境負荷の低減に加え、公正な労働条件、地域社会への貢献、経済的な実行可能性なども視野に入れます。
長期的な視点で、社会システム全体の持続可能性を追求するアプローチです。 -
サーキュラーデザイン: サステナブルデザインが目指す目標、特に環境的持続可能性を実現するための具体的な戦略の一つと位置づけられます。
エコデザインの提供する手法(例: リサイクルしやすい設計)を活用しつつ、特に資源循環と廃棄物・汚染の排除に強く焦点を当て、リニアエコノミーからの根本的なシステム変革を目指します。
エコデザインが「影響を減らす」ことを目指すのに対し、サーキュラーデザインは「そもそも廃棄物を出さない」システムを作ることを目指します。
まとめると、エコデザインは「より良く(Less bad)」、サステナブルデザインは「環境・社会・経済のバランス(Balance)」、サーキュラーデザインは「循環させる(Circular)システム変革」という点に、それぞれの主眼があると言えるでしょう。
環境にやさしいデザインとは何ですか?
「環境にやさしいデザイン」という言葉は、特定の学術的定義を持つというよりは、一般的に「環境に優しい」デザイン全般を指す、より広範で日常的な用語です。
エコデザインやグリーンデザインとしばしば同義で使われます。
具体的には、従来の製品や方法と比較して、何らかの点で環境への悪影響が少ないと考えられるデザインを指すことが多いです。
例えば、天然素材の使用、生分解性プラスチックの利用、省エネルギー設計、リサイクル材の活用などが含まれます。
サーキュラーデザインは環境配慮型デザインの一種ですが、逆は必ずしも真ではありません。
環境配慮型とされるデザインの中には、システム全体での資源循環や廃棄物ゼロを目指すサーキュラーデザインの原則を満たさないものも存在します。
サーキュラーデザインは、より包括的でシステム思考に基づいたアプローチと言えます。
サステナブルとエシカルの違いは何ですか?
「サステナブル(Sustainable)」と「エシカル(Ethical)」も混同されやすい言葉ですが、意味合いが異なります。
-
サステナブル (Sustainable): 「持続可能な」という意味で、主に環境、社会、経済の3つの側面において、将来世代の可能性を損なわずに現代世代のニーズを満たす、長期的なシステムの維持可能性を指します。
キーワードは「次世代」「長期性」「バランス」です。 -
エシカル (Ethical): 「倫理的な」「道徳的な」という意味で、法律だけでなく個人の良心や社会規範に基づいた正しい行動や判断を重視する考え方です。
人権、労働環境、動物福祉、環境保全、公正な取引などへの配慮が含まれます。
キーワードは「良識」「公正さ」「正しい行い」です。
両者は密接に関連しており、サステナブルな社会の実現にはエシカルな行動が不可欠であり、逆もまた然りです。
主な違いとして、サステナブルが「状態」や「結果(持続可能であること)」を重視するのに対し、エシカルは「行動原理」や「動機(倫理的であること)」をより重視する点にあります。
サーキュラーデザインの実践においても、リサイクルプロセスに関わる労働者の安全衛生や公正な処遇といったエシカルな配慮は、真に持続可能なシステムを構築するために不可欠な要素となります。
サーキュラーデザインの具体的な取り組み
サーキュラーデザインは、すでに様々な分野で具体的な取り組みが進められています。
ここでは、製品・サービス(特にファッション)と、建築分野での事例をご紹介します。
サーキュラーデザインの事例紹介
世界中の多くの企業が、サーキュラーデザインの原則を取り入れた製品開発やビジネスモデルの転換を進めています。
ファッション分野の事例
ファッション業界は、大量生産・消費・廃棄モデルからの転換が急務とされています。
-
MUD Jeans (オランダ): ジーンズのレンタルサービス(PaaS)を展開。
返却されたジーンズは修理・再レンタルされるか、リサイクルされて新しいジーンズの原料となります。
リサイクルを前提とした設計(例: プリントラベル)も特徴です。
ビジネスモデルと製品設計の両面からサーキュラリティを追求しています。 -
Fairphone (オランダ): モジュール設計を採用し、ユーザー自身が部品交換・修理できるスマートフォンを提供。
製品寿命の延長と電子廃棄物の削減を目指しています。
紛争鉱物を使用しないなど、倫理的な調達にも注力しています。 -
Patagonia (アウトドア用品): 「Worn Wear」プログラムによる製品修理サービスと中古品販売。
リサイクル素材や再生可能素材の利用も積極的です。
衣類を長く着用することの環境負荷削減効果も示唆されています。(※資料外情報:9ヶ月長く着用でフットプリント20-30%削減の可能性) -
ユニクロ (日本): 「RE.UNIQLO」プロジェクトで製品を回収し、リユース(難民支援など)やリサイクル(ダウン製品など)を実施。
リサイクルダウンはCO2排出量を約20%削減できると報告されています。 -
BRING (JEPLAN社, 日本): 独自の化学リサイクル技術でポリエステル衣類を再生。
石油由来原料比でCO2排出量を49%削減可能としています。
多くのブランドと連携し、クローズドループを目指しています。 -
Loop (リユース容器プラットフォーム): 大手メーカーと提携し、耐久性のある再利用可能容器で製品を提供するサービス。
使い捨て容器削減に貢献します。
ビジネスモデルの変革
製品設計だけでなく、ビジネスモデル自体も変化しています。
-
サブスクリプション/レンタル/PaaS: 製品を「所有」せず「利用」するモデル。
企業が製品の維持管理に責任を持つため、長寿命化や回収へのインセンティブが働きます。
(例: MUD Jeans, 家具・家電のサブスクリプション) -
シェアリングエコノミー: 資産(車、道具など)を共有し、利用効率を高めるモデル。
-
リセール/リコマース: 中古品の売買プラットフォームの活用。
建築分野におけるサーキュラーデザイン
建設業界は資源消費・廃棄物排出量が多いため、サーキュラーデザイン導入が強く求められています。
-
分解設計 (Design for Disassembly - DfD) と可逆性: 将来の解体・再利用を前提に、部材を容易に分離できるよう設計します。
接合方法の工夫や資材情報を記録するマテリアルパスポートの活用が含まれます。 -
既存建物の利活用 (Adaptive Reuse): 解体せずに改修・用途変更して再利用します。
資源消費と廃棄物を大幅に抑制できます。 -
再生・リサイクル材の利用: 解体発生材(コンクリート、木材など)や他産業廃棄物を建材として利用します。
(例: 鹿島建設のエコクリート®R3 ) -
バイオベース・再生可能素材の活用: 木材(CLT等)、竹、土など、再生可能で炭素貯蔵効果のある自然素材を利用します。
地域材の活用も重要です。 -
建物の長寿命化: 高耐久材料、維持管理計画、柔軟な設計により建物の寿命を延ばします。
建築分野では、新築だけでなく既存ストックの活用が鍵であり、設計段階での分解容易性やバイオベース素材の活用が重要性を増しています。
技術開発と設計思想の変革、サプライチェーン連携が求められます。
サーキュラーデザインまとめ
サーキュラーデザインは、リニアエコノミーから脱却し、資源が循環し続けるサーキュラーエコノミーを実現するための重要な設計思想です。
廃棄物・汚染の排除、製品・素材の価値維持を伴う循環、自然システムの再生という3原則に基づき、資源効率の最大化と環境負荷の最小化を目指します。
エコデザインやサステナブルデザイン、環境配慮型デザインとの違いを理解し、サステナブルやエシカルといった価値観とも連携しながら、より良い社会システムを構築していく必要があります。
ファッションや建築をはじめ、様々な分野で具体的な取り組みが進んでおり、環境負荷低減だけでなく、新たな経済価値やビジネスチャンスを生み出す可能性も秘めています。
当社では、循環型リサイクルとしてクローズドリサイクルというリサイクルシステムを提供しています。
自社内で発生する古紙やプラスチック廃棄物を回収し再度同じ製品としてリサイクルをする、環境に優しいリサイクルシステムです。
詳細は以下の記事や資料などをダウンロードいただき環境に優しい事業モデルを検討してみてはいかがでしょうか。
参考文献・出典:
-
エレン・マッカーサー財団 (Ellen MacArthur Foundation): https://www.ellenmacarthurfoundation.org/
-
世界のソーシャルグッドなアイデアマガジン IDEAS FOR GOOD : https://ideasforgood.jp/glossary/circular-design/
-
経済産業省 - 循環経済ビジョン2020: https://www.meti.go.jp/shingikai/energy_environment/junkai_keizai/pdf/20200522_02.pdf
-
環境省 - 循環経済への移行について: https://www.env.go.jp/recycle/circul/
関連資料はこちら
関連記事はこちら
~SHIFT ONではこんなサービスがご提供可能です~
SHIFT ON greenとは
SDGsやカーボンニュートラルなど、環境対応プロジェクトの企画から実行まで包括的に支援します。
関連ページ
SHIFT ONの関連サービスについてお問い合わせ
SHIFT ON greenでは環境・機能材ソリューションをご提案いたします。
まずはお気軽にお問い合わせよりどうぞ。
SHIFT ONについて、
もっと詳しく知りたい方へ
SHIFT ONのソリューションに
関するお問い合わせや、
資料のダウンロードはこちらで承ります。
持続可能な社会や事業に向けた行動変容に対して意識を「シフト」させるための取り組みを提案します。
紙製品に関する意外と知らない用語が詰まってます!
ぜひお役立ち用語集、ご活用ください。