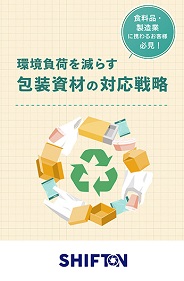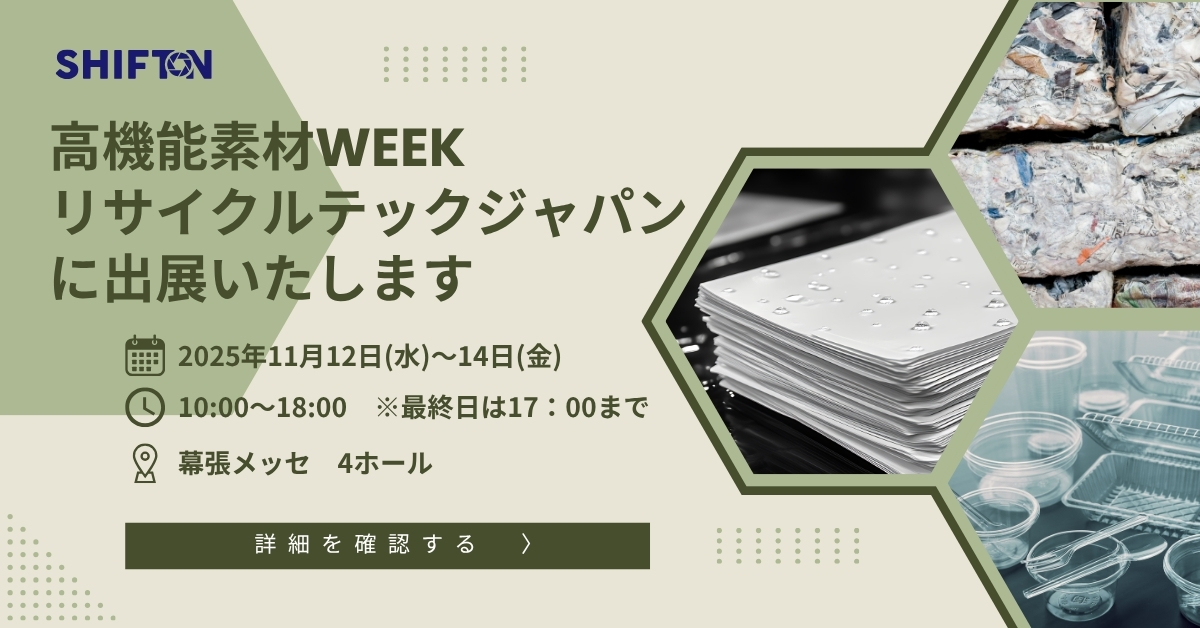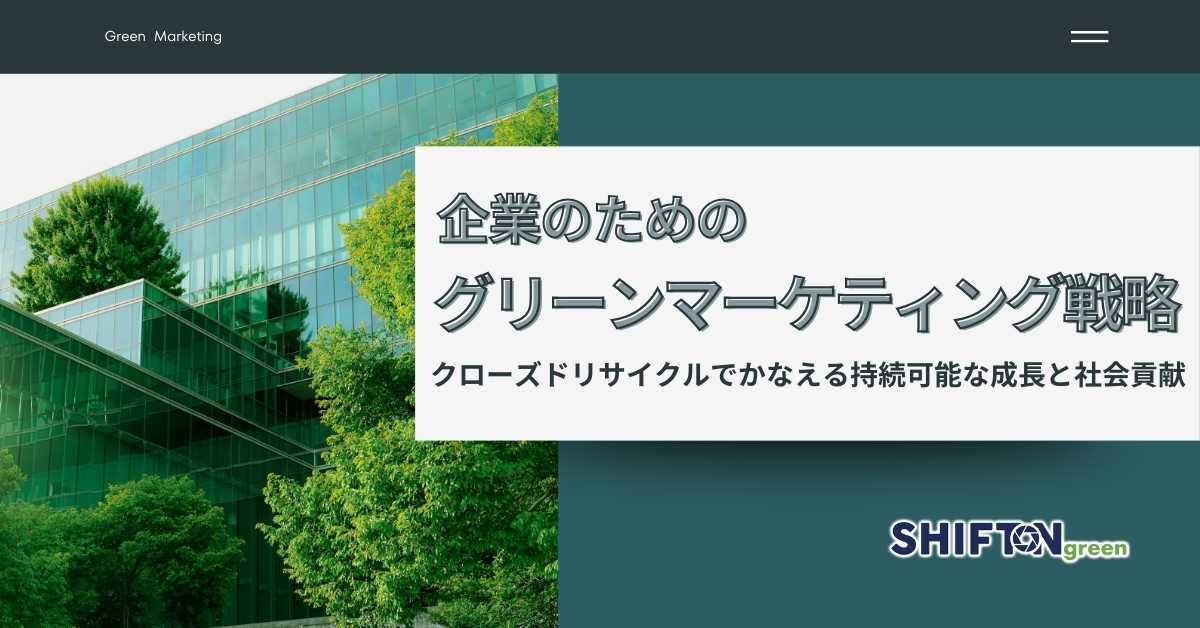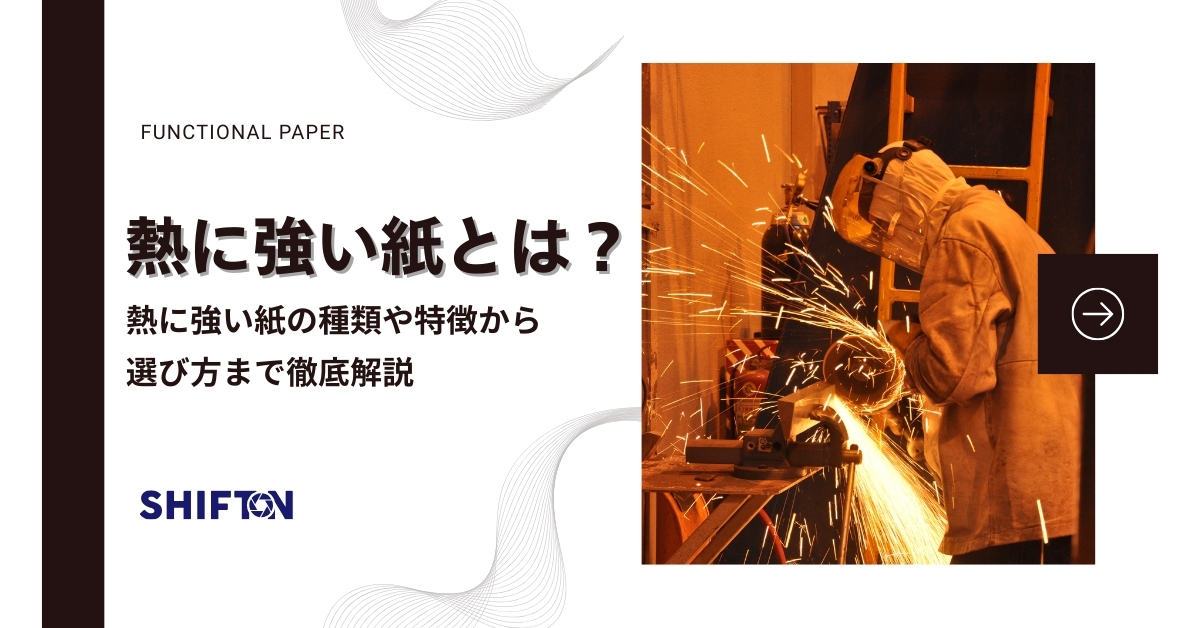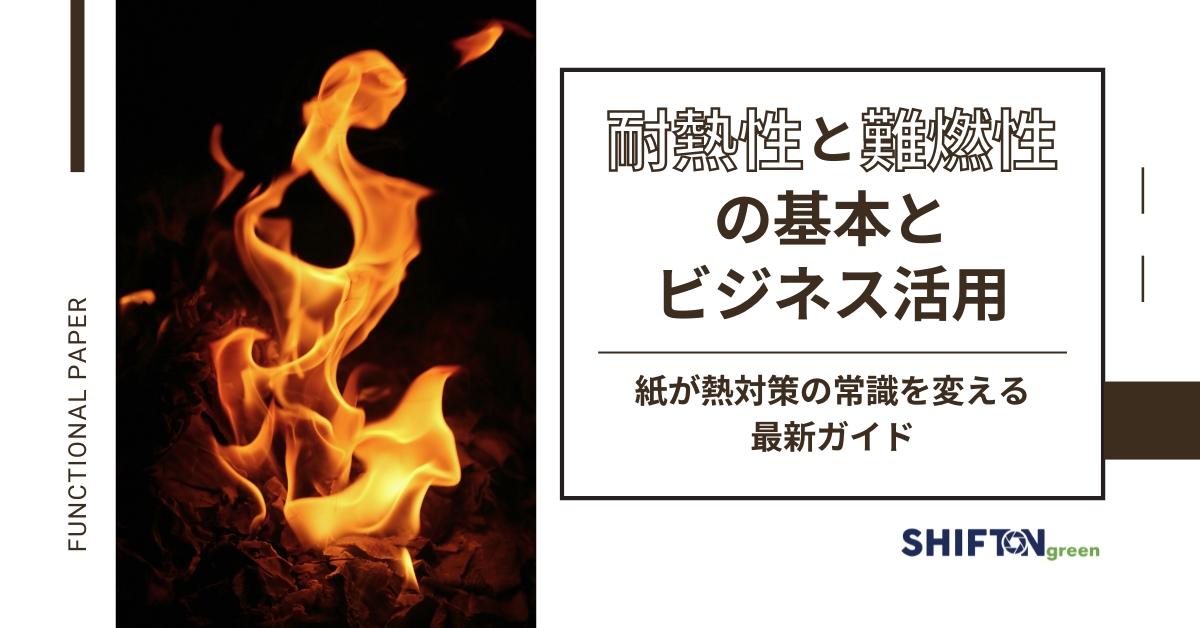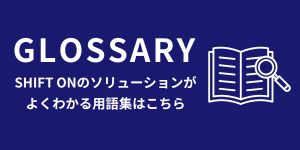拡大生産者責任(EPR)とは?取り組むメリットや推進の方法を解説

今、「つくる責任」という考え方が注目されています。
環境負荷の低減や資源循環に向けて、製品をつくる企業が廃棄やリサイクルまで責任を持つ「拡大生産者責任(EPR)」の考え方が、国内外で注目を集めているのです。
本記事では、拡大生産者責任の概要や国内外の取り組み、生産者・消費者・行政それぞれのメリットと課題をご紹介します。
拡大生産者責任(EPR)とは
拡大生産者責任(EPR:Extended Producer Responsibility)とは、生産者が製品の使用段階だけでなく、使用後に発生する廃棄物やリサイクルに対しても責任を持つという考え方です。
例えば、リサイクルしやすい素材を選ぶ、修理しやすい構造にする、回収体制を整えるなど設計段階での工夫を促すことで、廃棄物の削減やリサイクル率の向上につながるとされています。
拡大生産者責任は1990年代から世界各国で広まり、今では循環型社会を実現するうえで欠かせない存在です。

循環型社会基本法における基本理念の1つ
2000年に施行された「循環型社会形成推進基本法(循環型社会基本法)」は、廃棄物の発生をできるだけ抑え、再使用やリサイクルを促進し、資源を有効に循環させる社会を構築するために定められた法律です。
循環型社会を実現するための基本理念として、「排出者責任」と「拡大生産者責任」の2つの考え方が示されています。
排出者責任とは廃棄物の排出者が責任を負うもので、拡大生産者責任とは生産者が回収・処理に責任を持つものです。
その後、日本では容器包装リサイクル法や家電リサイクル法などの関連法が整備され、生産者による環境配慮の制度が進められてきました。
拡大生産者責任は、日本の循環型社会づくりに欠かせない基本的な考え方のひとつとして、現在も重要な役割を果たしています。
参考:環境省|循環型社会の形成に向けた法制度の施行状況
拡大生産者責任が生まれた背景
拡大生産者責任は、1990年にスウェーデンのトーマス・リンクヴィスト博士によって初めて提唱された考え方です。
博士は、環境負荷の高い製品が流通し続ける現状に対し、「製造者が製品の使用後まで責任を持つことで、環境に配慮した設計や回収が進む」と提言しました。
その背景には、深刻化する環境問題や、廃棄物処理にかかるコストの増大がありました。
とくにヨーロッパでは、限られた土地での処理問題や環境保全への意識が高く、EUをはじめとする国々で制度が導入され、成果をあげています。
こうした流れが世界に広がり、現在の制度設計の土台となっています。
拡大生産者責任(EPR)のメリット
拡大生産者責任(EPR)は、生産者が製品のライフサイクル全体に責任を持つことで、環境負荷の軽減や資源の有効活用につながる制度です。
この考え方を導入することで、廃棄物の削減だけでなく、行政や消費者にとってもさまざまなメリットが生まれます。
生産者・行政・消費者の三者にとってのメリットを整理しながら、拡大生産者責任の意義をあらためて見ていきましょう。

廃棄物処分量の削減
拡大生産者責任の導入により、生産者は製品の設計段階から「ごみになりにくい構造」や「リユース・リサイクルしやすい素材」を意識します。
その結果、廃棄物の発生量が抑えられ、リサイクル可能な資源として再利用される割合が増えることが期待されています。
また、生産者自身がリサイクル体制の整備や製品寿命の延長に取り組むことは、リサイクル率の向上にもつながります。
こうした循環を生み出すことで、廃棄物の最終処分量が減少し、環境への負荷を大きく軽減できます。
回収・廃棄・リサイクルにかかる負担の分散
これまで、使用済み製品の回収や処分は主に地方自治体が担い、費用や手間を負担することが一般的でした。
しかし拡大生産者責任の考え方によって、生産者側にもコストや責任が分担されることで、行政の負担が軽減されるだけでなく、生産者自身の責任意識や環境配慮の姿勢も高まります。
さらに、処理コストを抑えるために、より環境負荷の少ない製品設計や回収・再利用がしやすい構造への転換も促され、結果的に社会全体での負担軽減と効率化が進みます。
生産者のメリット
拡大生産者責任は環境保全に貢献するだけでなく、生産者にとっても新たな価値とメリットをもたらします。
企業のイメージ向上
これまで環境配慮に関する企業の取り組みは、消費者側からすると「見えにくい」「わかりにくい」といった側面がありました。
しかし、拡大生産者責任を通じて、使用後の容器回収やリサイクル、再生可能素材の使用といった取り組みを明確に伝えることが可能です。
環境意識の高い企業は、ブランド価値が向上します。
さらにSDGsへの貢献や透明性の高い姿勢は、消費者からの信頼にも結びつくでしょう。
ビジネスチャンスの創出
拡大生産者責任の枠組みのなかでは、エコ素材を使った製品や再利用可能なパッケージなど、環境を意識した新しい製品・サービスの開発が加速しています。
例えば、リースやサブスクリプションモデルの導入、リサイクル素材を活用した製品展開などがその一例です。
実際に、飲料メーカーではリサイクルPETを使用したボトルを導入することで、環境負荷の低減とともに消費者の支持を集めています。
消費者のメリット
拡大生産者責任は、生産者や行政だけでなく消費者にとってもメリットを感じやすい制度です。
環境保護への貢献
一消費者にとって、製品の廃棄後に目を向けて商品を選択することは難しく、選択の余地はほとんどありませんでした。
環境問題に関心が高い消費者ほど、ジレンマを感じやすかったと言えます。
しかし、拡大生産者責任が制度として定着すれば、情報収集も容易になります。
環境に配慮した製品を選ぶことで、間接的にごみの削減や資源循環に貢献できます。
日常の買い物の中に「環境の視点」を取り入れることは、消費者一人ひとりが社会の変化に関わる実感を持つことにもつながります。
拡大生産者責任(EPR)の推進に向けた取り組み事例
拡大生産者責任の考え方は、すでに多くの国と地域で制度として導入され、具体的な成果を上げています。
日本では法律による枠組みの整備、EU諸国ではより強い義務や負担金制度の導入など、それぞれの国が独自の形で拡大生産者責任を推進しています。
ここでは、日本と欧州における代表的な取り組みを紹介します。

日本:各種法律の制定
日本では、拡大生産者責任に基づいた法律が複数整備されています。
- 容器包装リサイクル法(1995年制定):消費者が容器を分別し、事業者がリサイクルを担うしくみを定めた法律
- 家電リサイクル法(2001年施行):特定家電4品目の回収・再資源化を製造業者に義務付けた制度
- 食品リサイクル法(2001年施行):食品廃棄物の再利用や発生抑制を事業者に求める法律
- プラスチック資源循環促進法(2022年施行):設計から回収までを対象に、3R+再生を推進する包括的な制度
関連記事:プラスチック資源循環促進法とは
欧州:登録義務化や環境負担金の支払いなど
ヨーロッパでは、日本よりも一歩進んだかたちでEPR(拡大生産者責任)制度が導入されています。
例えばドイツでは1991年に「容器包装廃棄物令」が施行され、2009年からはすべての製造事業者に対して、包装資材のライセンス登録が義務化されました。
また、EU加盟国では、洋服やカーテン、靴といった繊維製品に対しても、製造者に回収・リサイクルの責任を負わせる制度が広がっています。こうした製品にかかる廃棄物管理費用(環境負担金)を、生産者が支払う仕組みが一般化しており、リユースや再生可能素材へのシフトが促されています。
参考:OPTI|EU加盟国におけるEPRの規制状況と各国の具体的な取り組みについて
拡大生産者責任(EPR)の課題
拡大生産者責任は、持続可能な社会づくりに大きく貢献する制度ですが、導入と運用にはさまざまな課題も伴います。
ここでは、現場で実際に生じている生産者側の負担や、制度設計上の難しさ、そして消費者の関与の必要性について見ていきましょう。
生産者の負担が増加する
拡大生産者責任制度では、生産者が製品の廃棄やリサイクルに関する費用・体制を担うことが求められ、開発・運用にかかる手間やコストが増加傾向にあります。
とくに中小企業にとっては、新たな回収ルートの構築やリサイクル資材の選定などが負担となりやすく、導入へのハードルが高く感じられることもあるでしょう。
また、制度に参加せず恩恵だけを受けるただ乗りや、生産者の特定が困難な製品の存在も課題とされています。
効果的な制度設計が難しい
拡大生産者責任を効果的に機能させるためには、各国の環境政策や製品の特性、産業構造を踏まえた制度設計が求められます。
一律のルールでは現場の実態にそぐわない場合も多く、柔軟かつ現実的な設計が必要です。
また、国によって制度の成熟度に差があり、発展途上国では回収体制や再資源化の技術が整わず、形骸化してしまう恐れもあります。
さらに、現状では一部の国から他国へ廃棄物が輸出されるケースもあり、環境負荷の外部化という新たな問題も浮かび上がっています。
消費者への働きかけが必要になる
拡大生産者責任を成功させるためには、消費者の理解と協力が欠かせません。
リサイクル可能な製品を選ぶ、正しく分別する、リユース品を積極的に利用するなど、消費者の行動が制度の実効性を左右します。
消費者側の意識や行動が変わらなければ、環境配慮に取り組む生産者が評価されにくくなり、制度そのものの機能が弱まる可能性もあります。
制度の普及には広報活動や教育を通じた理解促進、消費者参加型の仕組みが重要です。
拡大生産者責任(EPR)の推進で重要なポイント
拡大生産者責任(EPR)を社会全体で機能させるためには、生産者・消費者・行政がそれぞれの立場から主体的に取り組むことが求められます。
たとえば消費者は、リユースやリサイクル製品を積極的に選び、自治体が定めた分別ルールに従って正しく廃棄を行うことが重要です。
また、環境に配慮した取り組みを行っている企業を選んで応援することも、間接的に拡大生産者責任の推進につながります。
行政においては、リサイクルの制度やインフラの整備が必要であり、啓発活動などを通じて市民や企業への理解を深める努力が欠かせません。
さらに、中小企業に対しては、制度導入の支援も求められます。
生産者は、製品設計の段階からリサイクルや再利用を考慮した開発を進めるとともに、使用済み製品の回収ルートを整える姿勢が大切です。
専門企業と連携したり業務を委託したりすることで、より実効性のある取り組みが可能になります。
拡大生産者責任(EPR)においてKPPができること
拡大生産者責任は、自社だけでの対応が難しい場面も多く、信頼できる専門パートナーとの連携が重要です。
KPPでは、拡大生産者責任の考え方に即した「クローズドリサイクル」や「脱プラ・紙化」といった、持続可能な循環型社会を支える具体的なソリューションを提供しています。
クローズドリサイクル
クローズドリサイクルとは、一度使用した製品を回収・再原料化し、生産者が再度同じ製品の原料として使用することです。
リサイクル工程で別の製品に加工される「オープンリサイクル」とは異なり、品質・用途を保ったままの循環が可能で、より効率的な資源の有効活用が期待できます。
導入時のメリットを解説

クローズドリサイクルのお客様への多くのベネフィットをご紹介
導入時に追加コストの心配がなく、環境への取り組みを導入しやすい。...
KPPでは、主に段ボールや洋紙を対象に取り組みを進めています。
紙以外にもプラスチックや金属の廃棄資材や梱包材も対象に含め、システムを構築しています。
廃棄物削減だけでなく、循環型ビジネスモデルへの転換も実現可能です。
脱プラ・紙化
近年、プラスチック資源に関する問題が社会的にも注目を集めており、拡大生産者責任の観点からも「脱プラスチック」への対応が急務となっています。
KPPでは、プラスチックの使用削減に向けて、以下のような素材や技術を用いた提案を行っています。
- NEQAS OCEAN:酢酸セルロースを主原料とする環境対応樹脂
- バイオPP:キャッサバ澱粉を添加したバイオマスプラスチック
- Minima PLA:ポリ乳酸(PLA)を主成分とする生分解性プラスチック
さらに、包装資材を紙素材に置き換える「紙化」にも対応し、再資源化しやすく、廃棄物削減にもつながる環境配慮型の素材選びをサポートしています。
拡大生産者責任の推進ならKPPにご相談を
拡大生産者責任(EPR)は、循環型社会の実現に向けた重要な制度として、今後ますます求められる考え方です。
KPPでは、拡大生産者責任の推進に役立つクローズドリサイクルや脱プラ・紙化といったソリューションを多数ご用意しています。
具体的な事例は、以下の資料からご確認いただけます。
「何から始めればよいかわからない」という方も、まずはお気軽にご相談ください。
詳しくお問い合わせご希望の方はこちら
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。