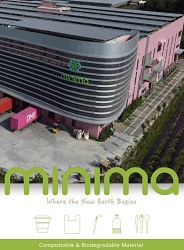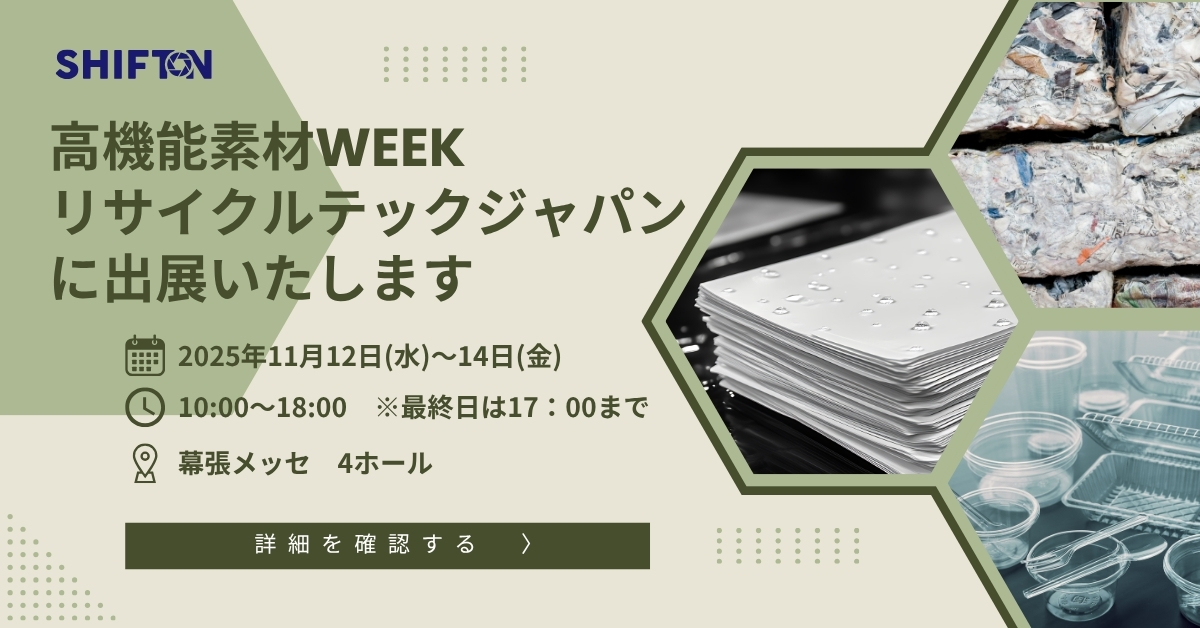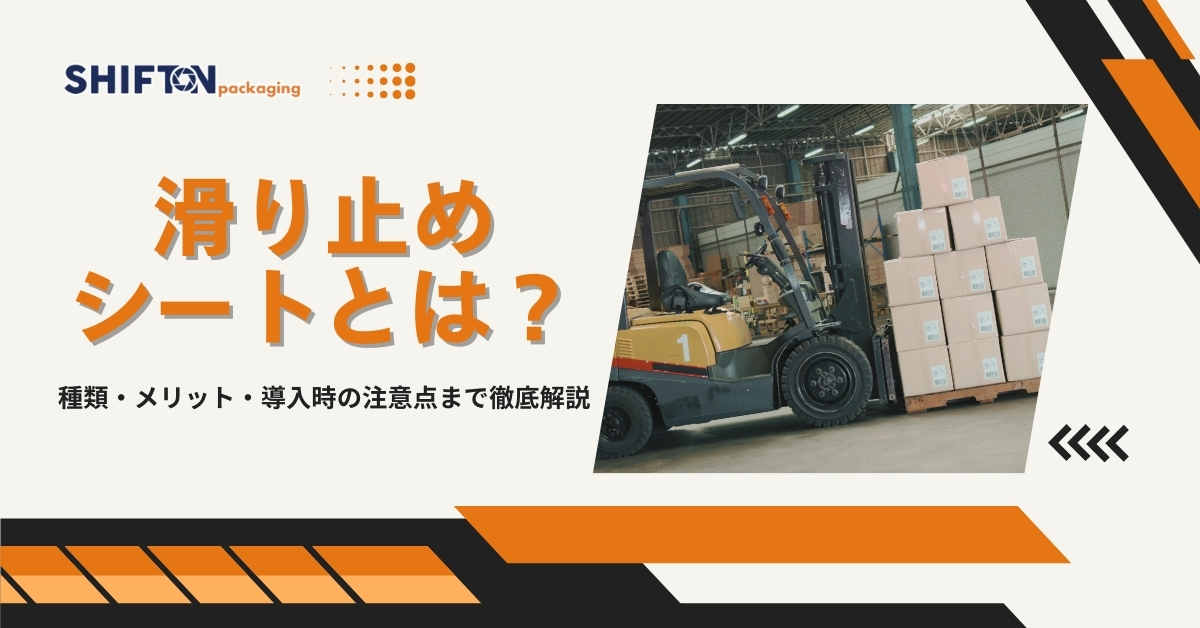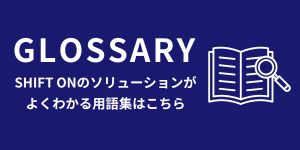企業の未来を拓く、SDGs「つくる責任つかう責任」の実践ガイド

現代のビジネス環境において、SDGs(持続可能な開発目標)への取り組みは、もはや単なる社会貢献活動ではありません。
企業の存続と成長に不可欠な経営戦略そのものとなっています。
特に、目標12に掲げられた「sdgs つくる責任つかう責任」は、企業の事業活動の根幹に関わる重要なテーマです。
大量生産・大量消費・大量廃棄という従来型の経済モデルが限界を迎え、食品ロスやプラスチックごみといった問題が深刻化するなか、企業には持続可能な生産と消費のパターンを確立する「つくる責任」が、そして私たちには賢明な消費選択を行う「つかう責任」が求められています。
この記事では、「sdgs つくる責任つかう責任」の現状と課題を深く掘り下げ、日本や世界の企業がどのような取り組みを行っているのか、具体的な事例を交えながら解説します。
自社のサステナビリティ経営を加速させ、新たな企業価値を創造するためのヒントがここにあります。
SDGsにおける「つくる責任つかう責任」の重要性
SDGs目標12「つくる責任つかう責任」は、持続可能な社会を実現するための要となる目標です。
私たちの経済活動が地球環境に与える影響を直視し、生産と消費のあり方を根本から見直すことを求めています。
このセクションでは、その現状と課題、そして私たちの生活が地球にどれほどの負荷をかけているのかを明らかにします。
sdgs つくる責任つかう責任の現状

世界は今、資源の過剰な消費という大きな課題に直面しています。
特に先進国の経済活動は、多くの資源を消費することで成り立っており、その結果として大量の廃棄物を生み出しています。
この「大量生産・大量消費・大量廃棄」のモデルは、資源の枯渇や環境汚染を引き起こし、持続可能な社会の実現を阻む大きな要因となっています。
日本も例外ではありません。
国際的な評価では、日本のSDGs目標12の達成状況は最も低い「レッド」評価を受けており、目標達成に向けて「重大な課題」があると指摘されています。
特に、一人当たりの使い捨てプラスチック容器包装の廃棄量は世界で2番目に多いという不名誉なデータもあります。
このままのペースで廃棄を続ければ、日本の最終処分場はあと約22年で満杯になるとも懸念されており、対策は待ったなしの状況です。
表1:世界の1人当たりプラスチック容器包装の廃棄量(2019年)
| 国・地域 | 1人当たりの廃棄量(kg/年) |
|---|---|
| アメリカ | 45.0 kg |
| 日本 | 37.0 kg |
| EU | 32.0 kg |
| 中国 | 18.0 kg |
| 世界平均 | 29.0 kg |
出典:国連環境計画(UNEP)等のデータを基に作成
つくる責任つかう責任は地球何個分?

私たちの現在の消費生活が、地球の許容量をどれだけ超えているかを示す指標に「エコロジカル・フットプリント」があります。
これは、人間の活動を支えるために必要な資源を生み出し、廃棄物を吸収するために必要な土地と水域の面積を示すものです。
この指標で計算すると、現在の人類全体の生活を支えるためには、地球が1.7個必要であるとされています。
これは、地球が1年かけて再生する資源を、人類が1年経たずに使い果たしている「オーバーシュート」という状態を意味します。
さらに衝撃的なのは、日本の状況です。
もし世界中の人々が、現在の日本人と同じ水準の生活を送った場合、地球が2.8個も必要になると試算されているのです。
この数値は、日本の消費スタイルがいかに持続可能でないかを明確に示しています。
また、この負荷は国内でも一様ではありません。
例えば、東京都民の生活レベルでは地球3.1個分が必要なのに対し、山梨県民の生活レベルでは2.4個分となり、都市部の生活がいかに環境負荷が大きいかがわかります。
これは、日本の経済的繁栄が、未来の世代や他国の資源を先食いすることで成り立っているという厳しい現実を突きつけています。
つくる責任つかう責任の問題
「つくる責任つかう責任」が問われる背景には、私たちの生産・消費活動が引き起こす数々の深刻な問題があります。
1. 資源の枯渇
私たちは、石油や天然ガス、石炭といった有限な化石資源に大きく依存しています。
このままのペースで消費を続ければ、石油はあと約53.5年、天然ガスは約48.8年で枯渇するとも予測されており、将来のエネルギー供給が危ぶまれています。
水資源も例外ではなく、私たちが利用できる淡水は地球上の水のわずか0.5%に過ぎません。
2. 環境汚染
大量生産・大量消費は、地球環境に深刻なダメージを与えています。
特にプラスチックごみ問題は深刻で、適切に処理されなかったプラスチックが河川を通じて海に流出し、海洋生態系を破壊しています。
日本は一人当たりのプラスチック容器包装の廃棄量が世界で2番目に多く、この問題に対する責任は大きいと言えます。
また、食品廃棄物の焼却は多くの二酸化炭素を排出し、地球温暖化を加速させる一因となっています。
3. 食料問題と貧困
世界では生産される食料の約3分の1が廃棄されている一方で、7人に1人の子どもが貧困で食事に困っているという矛盾した状況があります。
日本で年間に廃棄される食料(食品ロス)は、世界中で飢餓に苦しむ人々への食料援助量の約2倍にも相当します。
食料を無駄にすることは、倫理的な問題であると同時に、生産に費やされた資源を無駄にし、世界の食料安全保障を脅かす行為なのです。
これらの問題は相互に関連し合っており、解決するためには生産から消費、廃棄に至るまでのシステム全体を変革することが不可欠です。
企業が実践する「sdgs つくる責任つかう責任」の取り組み
地球規模の課題解決に向けて、国や自治体だけでなく、企業の役割がますます重要になっています。
特に「つくる責任」を担う企業は、事業活動を通じて持続可能な社会への変革をリードする力を持っています。
ここでは、日本や世界の企業がどのように「sdgs つくる責任つかう責任」に取り組んでいるのか、具体的な事例とともに見ていきましょう。
つくる責任つかう責任 日本の取り組み
日本政府は、SDGs目標12の達成に向けて、さまざまな法律や戦略を整備し、国全体での取り組みを推進しています。
- 食品ロス削減推進法(2019年施行): 国、自治体、事業者、消費者が連携し、社会全体で食品ロス削減に取り組むことを目指す法律です。
- 食品リサイクル法(2000年制定): 食品関連事業者に対し、食品廃棄物の削減と再生利用を義務付けています。
- プラスチック資源循環促進法(2022年施行): 製品の設計から廃棄物の処理まで、プラスチックのライフサイクル全体での資源循環(3R + Renewable)を促す法律です。
コンビニのスプーンやフォークの有料化などもこの法律に基づいています。 - プラスチック資源循環戦略: 2030年までにワンウェイプラスチックを累積25%排出抑制し、2035年までには使用済みプラスチックを100%有効利用するなど、野心的な目標(マイルストーン)を掲げています。
これらの法整備により、企業は廃棄物の削減やリサイクルへの対応をより一層求められるようになっています。
しかし、日本の取り組みはまだ道半ばであり、特に廃棄物問題や食品ロスなど、解決すべき課題は山積しています。
法律や戦略を実効性のあるものにするためには、企業の積極的な行動が不可欠です。
sdgs つくる責任つかう責任 取り組み

企業が「つくる責任」を果たすための取り組みは多岐にわたります。
これらはコストではなく、新たなビジネスチャンスや企業価値向上に繋がる投資として捉えることが重要です。
主な取り組みの方向性
- 3Rの徹底:
- リデュース(削減): 製品の軽量化、包装の簡素化、そもそも廃棄物が出ない製造プロセスの構築。
- リユース(再利用): 詰め替え製品の提供、修理しやすい製品設計、レンタルやシェアリングサービスの導入。
- リサイクル(再生利用): リサイクルしやすい素材の採用、使用済み製品の回収システムの構築。
- サステナブルな素材の利用: 再生素材や、植物由来のバイオマスプラスチックなど、環境負荷の低い素材への切り替え。
- 再生可能エネルギーの導入: 工場やオフィスの電力を太陽光発電などの再生可能エネルギーに切り替え、CO2排出量を削減する。
- サプライチェーン全体の改革: 環境に配慮した調達基準を設け、取引先にも協力を求めることで、サプライチェーン全体での持続可能性を高める。
- 情報開示と消費者啓発: 製品の環境情報を積極的に開示し、消費者が賢い選択(エシカル消費)をできるようサポートする。
これらの取り組みを統合し、経済活動全体を「取って、作って、捨てる」という線形経済(リニアエコノミー)から、資源を循環させ続ける「循環型経済(サーキュラーエコノミー)」へと転換していくことが、究極の目標となります。
つくる責任つかう責任の具体例は?
世界中の先進的な企業は、すでに「つくる責任」を事業戦略の中核に据え、具体的なアクションを起こしています。
ここでは、様々な業界の取り組み事例を紹介します。
| 企業名 | 業界 | 主な取り組み内容 |
|---|---|---|
| ユニクロ(ファーストリテイリング) | アパレル | 不要になった自社製品を回収し、難民支援としてリユースしたり、燃料や素材としてリサイクルしたりする「RE.UNIQLO」プロジェクトを推進。 |
| Apple | エレクトロニクス | 製品に使用する素材の再生素材比率を高め(2022年時点で20%)、サプライヤーにも再生可能エネルギーの使用を要請。 使用済み製品の回収・リサイクルプログラムも大規模に展開。 |
| セブン&アイ・ホールディングス | 小売 | 販売期限が近い商品を選ぶ「てまえどり」の推奨や、全国の店舗にペットボトル回収機を設置。 オリジナル商品の容器を環境配慮型素材へ切り替える目標も設定。 |
| メルカリ | IT・プラットフォーム | 個人間でのモノの再利用(リユース)を促進するフリマアプリ事業そのものが循環型経済に貢献。 繰り返し使える梱包材「メルカリエコパック」も開発。 |
| ナイキ | スポーツ用品 | 製品の75%以上に再生素材を活用。 デザイン段階から廃棄物を最小限に抑える工夫や、環境にやさしい素材の開発に取り組む。 |
| ミツカングループ | 食品 | 京都市と連携し、野菜の皮や芯まで使い切る「もったい鍋®」などのレシピを開発・公開。 家庭での食品ロス削減を促進。 |
これらの事例からわかるように、「つくる責任」への取り組みは、企業の規模や業種を問わず、あらゆる事業活動において実践可能です。
つくる責任つかう責任 食品ロス

食品ロスは、「つくる責任つかう責任」の中でも特に深刻で、身近な問題です。
日本では、まだ食べられるのに捨てられてしまう食品が、2023年度で464万トンにも上ります。
このうち、製造・小売・外食などの事業活動から発生する「事業系食品ロス」は231万トンを占めており、企業の責任は重大です。
この問題に対し、多くの企業が知恵を絞って対策を進めています。
企業の食品ロス削減へのアプローチ
- 需要予測の高度化: 日本マクドナルドでは、過去の販売データや天候などからAIが需要を予測し、食材の過剰な発注を防いでいます。
- 規格外品の活用: 吉野家では、牛丼に使用する玉ねぎの端材を粉末化し、パンの原料として供給するアップサイクルに取り組んでいます。
規格外の野菜や果物を積極的に仕入れ、ジュースや加工品として販売する企業も増えています。 - 賞味期限の延長・表示の見直し: キユーピーや日清食品などは、容器包装の技術や製造工程の改善により、製品の賞味期限を延長。
また、賞味期限の表示を「年月日」から「年月」に切り替えることで、すぐに廃棄されるのを防いでいます。 - フードシェアリングサービスの活用: コークッキングが運営する「TABETE」や、クラダシが運営するECサイト「Kuradashi」は、廃棄の危機にある食品を、必要とする消費者に割引価格で繋ぐプラットフォームです。
多くの飲食店や小売店がこれらのサービスを活用しています。 - フードバンクへの寄付: ニッスイグループなどは、品質に問題はないものの、印字ミスなどで販売できなくなった商品をフードバンクに寄付し、食料を必要とする人々を支援しています。
これらの取り組みは、廃棄コストの削減に直結するだけでなく、企業の社会的評価を高める上でも非常に有効です。
資源を無駄にしない取り組みは?
食品ロスと並ぶ大きな課題が、プラスチックをはじめとする資源の廃棄問題です。
日本は廃プラスチックの「有効利用率」が86%(2020年)と高い数値を公表していますが、その内実には注意が必要です。
この「有効利用」の約6割は、ごみを燃やしてその熱を発電などに利用する「サーマルリサイクル」で占められています。
サーマルリサイクルは、ごみの体積を減らし、埋立地の延命に貢献する一方で、資源そのものは燃やして失われ、CO2を排出します。
ヨーロッパなどではリサイクルと見なされておらず、この手法に大きく依存していることが、日本の循環型社会への移行を阻む一因とも言われています。
真の資源循環のためには、以下のリサイクル手法の比率を高めることが不可欠です。
- マテリアルリサイクル: 廃プラスチックを洗浄・粉砕し、再びプラスチック製品の原料として利用する手法。
物理的な再生。 - ケミカルリサイクル: 廃プラスチックを化学的に分解し、分子レベルの原料に戻してから再利用する手法。
品質の劣化なく再生が可能。
この課題に対し、企業も動き出しています。
例えば、三菱ケミカルとENEOSは共同で、廃プラスチックを油に戻して化学原料として再生する、国内最大級のケミカルリサイクル設備を建設しています。
このような技術革新こそが、資源を無駄にしない社会の実現に向けた鍵となります。
企業には、自社の製品が使用後にどのように処理されるかまでを視野に入れ、マテリアルリサイクルやケミカルリサイクルがしやすい製品設計(サーキュラーデザイン)を行うことが求められています。
作る責任使う責任 私たちにできること
持続可能な社会の実現は、企業(つくる側)の努力だけでは達成できません。
私たち消費者(つかう側)一人ひとりの行動が、市場を変え、社会を動かす大きな力となります。
企業は、消費者が環境に配慮した行動を取りやすくなるような製品やサービスを提供することが重要です。
消費者ができること(5R)
- Refuse(リフューズ/断る): 不要なレジ袋や過剰な包装、使い捨てカトラリーを断る。
- Reduce(リデュース/減らす): 本当に必要なものだけを、必要な量だけ購入する。
食べ残しをしない。 - Reuse(リユース/再利用する): マイバッグやマイボトルを持参する。
詰め替え製品を選ぶ。
リサイクルショップやフリマアプリを活用する。 - Repair(リペア/修理する): 壊れたものを安易に捨てず、修理して長く使う。
- Recycle(リサイクル/再生利用する): 地域のルールに従って正しく分別する。
リサイクル素材から作られた製品を選ぶ。
企業は、こうした消費者の行動を後押しする責任があります。
例えば、修理サービスの提供、リサイクルしやすい単一素材での製品開発、環境負荷に関する情報の分かりやすい表示(ラベリング)などが挙げられます。
消費者が「エシカル消費(倫理的消費)」、つまり環境や社会に配慮した商品やサービスを積極的に選ぶようになれば、それが市場のスタンダードとなり、持続可能な取り組みを行う企業が正当に評価される社会が実現します。
まとめ:企業の未来を創る「sdgs つくる責任つかう責任」
本記事では、SDGs目標12「sdgs つくる責任つかう責任」について、その現状から国内外の企業の具体的な取り組みまでを幅広く解説してきました。
大量生産・大量消費モデルがもたらした食品ロスやプラスチックごみ問題は、もはや看過できないレベルに達しており、私たちの生活基盤そのものを脅かしています。
このような状況下で、企業が「つくる責任」を果たすことは、社会的な要請であると同時に、自社の持続的な成長を実現するための重要な経営戦略です。
資源を効率的に利用し、廃棄物を削減する取り組みは、コスト削減や新たなビジネスチャンスの創出に繋がります。
そして、環境や社会に配慮した製品・サービスは、消費者の信頼を獲得し、企業ブランドの価値を大きく向上させるでしょう。
この変革の時代において、貴社のサステナビリティへの取り組みを強力にサポートするのが、私たち国際紙パルプ商事株式会社が運営するソリューションブランド「SHIFT ON」です。
SHIFT ONは、お客様の課題に焦点をあて、最適な解決策をご提案します。
- 先進的なバイオプラスチックの利用促進: 化石資源由来のプラスチックからの脱却を支援するため、最先端のバイオプラスチックをご提案します。
- NEQAS OCEAN: 海洋マイクロプラスチック問題の解決に貢献する、海洋生分解性に優れたバイオマス素材です。
従来の環境配慮型樹脂の課題であった透明度を解消し、高い透明性を実現。
さらに、高いリサイクル性能と抗菌作用も持ち合わせており、釣り具や食器、化粧品容器など幅広い製品への応用が可能です。
- minimaPLA: 従来のPLA(ポリ乳酸)樹脂が持つ「耐熱性の低さ」「衝撃への弱さ」といった弱点を、独自の配合技術で克服した高機能バイオプラスチックです。
既存の製造ラインをそのまま活用できるため、大規模な設備投資なしで環境配慮型製品への切り替えを実現し、サステナブルな製品化を加速させます。
- NEQAS OCEAN: 海洋マイクロプラスチック問題の解決に貢献する、海洋生分解性に優れたバイオマス素材です。
- クローズドリサイクル: お客様の事業所から排出される使用済み段ボールなどの古紙を回収し、再び製品の原料として循環させる「クローズドリサイクル」の仕組みを構築します。
廃棄物を価値ある資源に変え、安定的な資材調達と環境貢献を両立させます。
「つくる責任」への取り組みは、未来への投資です。
SHIFT ONは、紙の専門商社として長年培ってきた知見とグローバルなネットワークを活かし、素材の提案から循環の仕組みづくりまで、お客様の「ありたい未来」の実現に向けて伴走します。
持続可能な社会と事業の成長を、私たちと一緒に実現しませんか。
まずはお気軽にご相談ください。