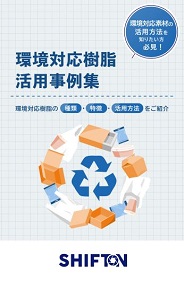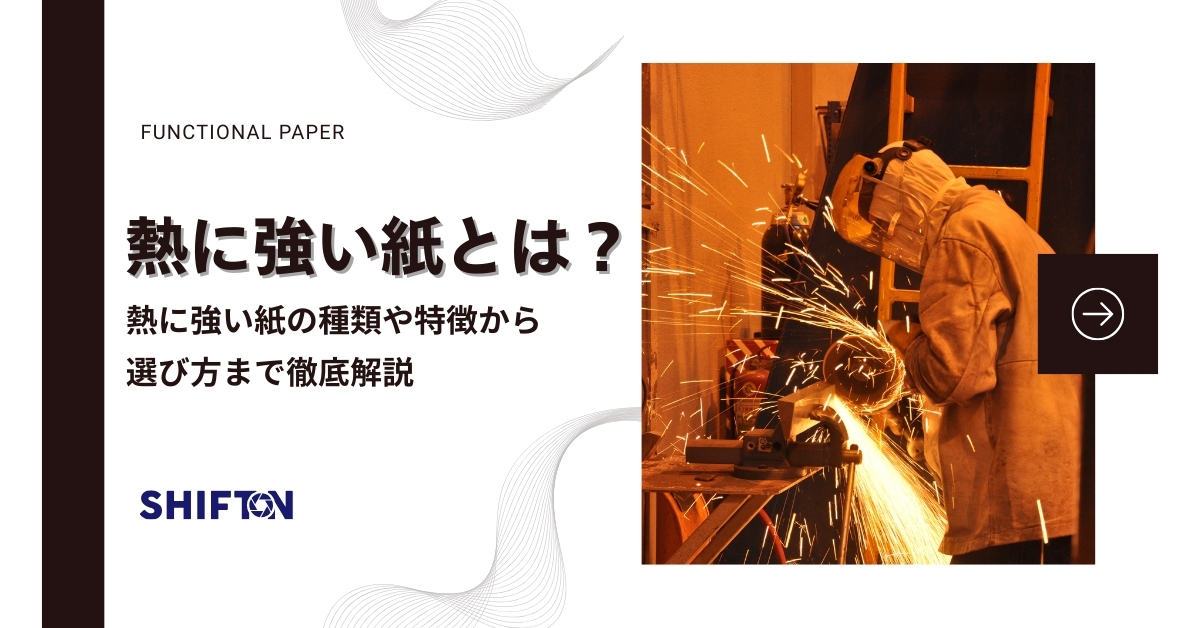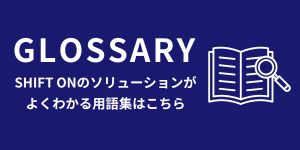「サステナブル経営に不可欠|企業の脱プラスチックの取り組みと支援制度の全体像」
最終更新日:2025/10/17

脱プラスチック(プラスチック使用量・廃棄量削減)は、持続可能な資源循環社会の実現に向けた重要なアプローチです。
環境省は、2018年に「プラスチック・スマート」運動をスタートし、企業・自治体・個人による取り組みは約3500件登録されています。
また2022年にはプラスチック資源循環法(プラ新法)が施行され、製造・設計・使用・廃棄にわたる企業の責任が明確化されました。
さらなるプラスチックの使用量削減、海洋プラスチックごみの削減が求められるなか、行政の支援にどのようなものがあるか、実際に企業はどのような取り組みをしているかなど、事例を中心にご紹介していきます。
行政主導の支援制度とガイドライン
脱プラスチックの流れを加速するうえで、行政の主導による制度設計と支援施策は欠かせません。日本政府は法整備だけでなく、ガイドラインの策定や補助金制度を通じて、企業の自主的な取り組みを後押ししています。以下では、主に環境省・経済産業省・消費者庁による施策を詳しく解説します。
経済産業省|資源循環補助金・再資源化設備導入の支援
経済産業省は、プラスチックリサイクルやバイオプラスチックの導入を加速するため、複数の補助金・助成制度を運用しています。例に廃プラスチックの資源循環高度化事業補助金やバイオプラスチック導入促進事業があります。
環境省|ガイドラインとプラスチック・スマート施策
環境省は、プラ新法に対応した実務的なガイドラインやチェックリストを策定・公開し、企業の自主対応を支えています。なかでも2018年から行われているプラスチック・スマートは脱プラスチックに向けた企業・自治体・NPOなどの優良事例を見える化し、社会全体での取り組みを推進しています。
当社では賛同商品となっている紙製ハンガーを提供しています。
石油由来素材から紙素材への詳細資料はこちら

紙製のフェイスカバーで洋服試着をサステナブルでもっと快適に!
従来のフェイスカバーなどが問題視される中、紙製の脱プラツールが持つ環境に優しい特性を、今回は詳しくご紹介したいと思います。...
プラスチック等資源循環システム構築実証事業に
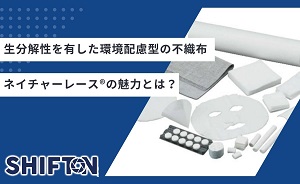
採択された製品はこちら
生分解素材である不織布・ネイチャーレース®は、海洋中で分解する性能を持つため、...
消費者庁|環境表示への監視と企業への指導
消費者庁は、企業が製品に記載する環境表示(例:生分解性・堆肥化可能・エコ素材使用)について、環境表示に対する監視と是正を強化しています。
実際には一定の条件下でしか分解しない素材を「土に還る」と表示、一部にしか再生素材が使われていないのに「全体がリサイクル」と表現することは景品表示法違反にあたります。
企業にはグリーンウォッシュにならないよう、表示内容の根拠となる科学的データ・試験結果の保持、具体的な素材の配合比率や分解条件の明記が求められます。
企業の具体的な脱プラスチック取り組み事例
脱プラスチックの実現には、行政の施策だけでなく、企業による自主的な取り組みが不可欠です。
ここでは、業種を問わず先進的な活動を行っている企業の事例を詳しく紹介します。
容器軽量化・リサイクル素材活用
森永製菓は、主力製品である「inゼリー」シリーズの容器構造を見直し、ストロー部・キャップ部を含めたプラスチック使用量を約9%削減しました。容器素材には再生可能な樹脂を一部導入し、食品の安全性を確保しながら環境負荷を低減しています。
※出典:森永製菓株式会社「容器・包装における環境配慮の推進」(閲覧:2025/07/01)
使い捨て削減・リユース容器の普及
トヨタ自動車はオフィスや社内売店で、使い捨てプラスチックを紙製品に切り替えています。また環境部内では、廃車エアバッグから制作したエコバッグ(AIR RE:BAG)を活用したシェアリングを実施しています。
※出典:トヨタ自動車株式会社「オフィスでの使い捨てプラスチック削減取り組み」(閲覧:2025/07/01)
マイクロプラスチック流出抑制の取り組み
当社では紙から生まれた天然繊維OJO⁺を使用した人工芝を展開しています。
マイクロプラスチックの流出を抑えるだけではなく、そもそも発生をさせないことに着目し作られた製品です。
安全性・機能性にも優れ、快適な空間を創造します。
関連記事はこちら

人工芝によるマイクロプラスチック問題を解決する紙製人工芝のご紹介
マイクロプラスチックの流出を抑えるだけではなく、そもそも発生をさせないことに着目しました。...
企業間の連携と目標設定
WWFジャパンが発足した「プラスチック・サーキュラー・チャレンジ2025」は、業界の垣根を越えた企業連携による脱プラスチック推進プログラムです。参画企業全12社は以下のような定量目標を設定し、2025年までに達成を目指しています。
- 使い捨てプラスチック使用量の25%削減
- リユース容器の導入率20%以上
- プラスチック包装における再生材・バイオ素材比率の50%以上
CSRの枠を超えた戦略的な環境経営として、多くの注目を集めています。
※出典:公益財団法人 世界自然保護基金ジャパン「企業の枠組み「プラスチック・サーキュラー・チャレンジ2025」による「みらいへの約束」イベント開催報告」(閲覧:2025/07/01)
企業での脱プラスチックの取り組みまとめ
脱プラスチックは、今や一部の先進企業や環境団体だけの課題ではなく、すべての業界・組織・生活者に求められる共通のテーマです。
企業側は、容器の軽量化やリユース容器の導入、マイクロプラスチック抑制の素材開発など、業種や規模を問わず、自社にあったアプローチを取り入れています。
コストではなく「ブランド価値と信頼性の向上につながる投資」と捉え、持続可能な社会構築のためにともに実践していきませんか。
参考:(閲覧:2025/07/01)
・経済産業省:廃プラスチックの資源循環の高度化に資する取組への支援
・経済産業省:バイオプラスチック導入ロードマップ
・環境省:「プラスチック・スマート」キャンペーンの取組について
・環境省:マイクロプラスチック削減に向けたグッド・プラクティス集
・消費者庁:より良い商品・サービスを安心して選ぶために
・プラスチック資源循環:「容器包装のプラスチック資源循環等に資する取組事例集」(約30社72事例)をプラスチック関連ファクトデータ集のページに掲載しました。