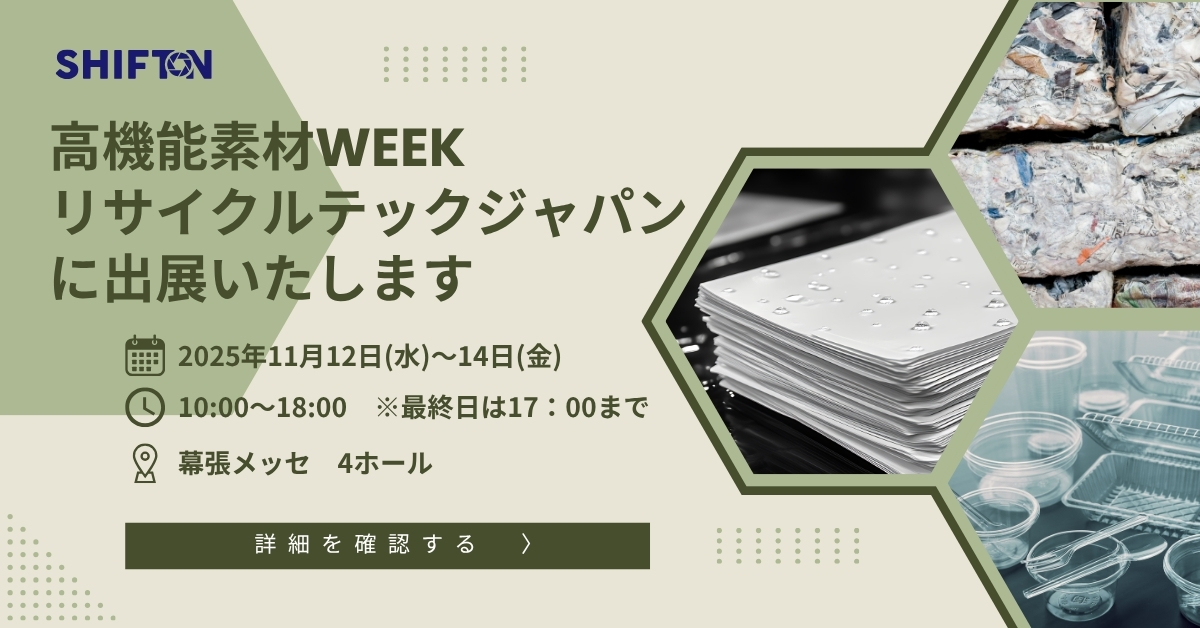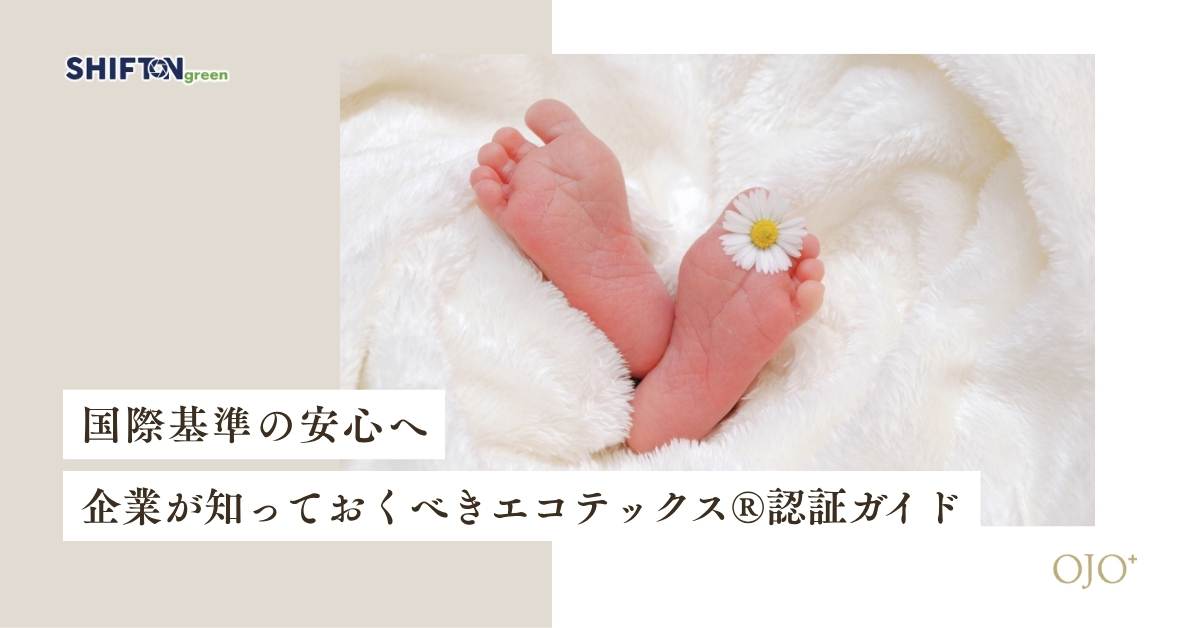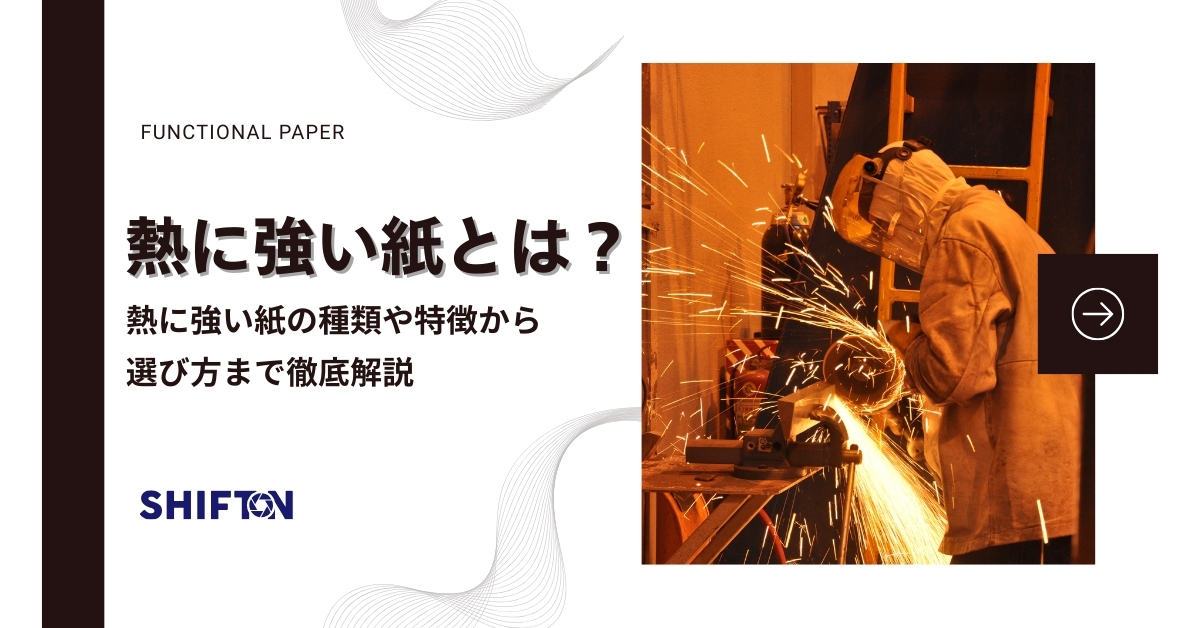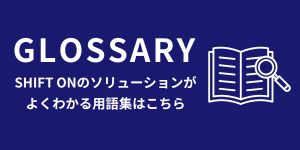SDGs目標14「海の豊かさを守ろう」|企業が牽引する持続可能な海洋の未来への取り組み

私たちの地球にとって、海は生命の源であり、豊かな生態系を育むかけがえのない存在です。しかし、近年、プラスチック汚染、乱獲、気候変動の影響などにより、海の環境は深刻な危機に瀕しています。このような状況の中、SDGs(持続可能な開発目標)の目標14「海の豊かさを守ろう」は、持続可能な社会を実現するために、私たち一人ひとりはもちろん、特に企業にとって喫緊の課題となっています。
本記事では、SDGs目標14「海の豊かさを守ろう」取り組みの重要性とその背景を分かりやすく解説し、世界や日本、国連の取り組み事例や企業が果たすべき役割と具体的なソリューションをご紹介します。
SDGs目標14「海の豊かさを守ろう」とは?内容を分かりやすく解説
SDGs目標14の「海の豊かさを守ろう」は、海洋と海洋資源を保全し、持続可能な形で利用することを目指す目標です。
具体的には、海洋汚染の防止・削減、海洋・沿岸生態系の回復、海洋酸性化の影響最小化、水産資源の保護(過剰漁業・違法漁業の抑制)、開発途上国の経済的便益の増大、海洋技術の移転促進、国際法の順守といった多岐にわたる10のターゲットによって構成されています。
この目標は、単に海の環境を守るだけでなく、海の恵みに依存する人々の生活や経済活動の持続可能性も視野に入れています。
海洋環境が直面する深刻な課題
現在、海洋環境は以下のような多岐にわたる課題に直面しています。
- 海洋プラスチック汚染:
毎年数百万トンものプラスチックごみが海に流入し、海洋生物に深刻な影響を与えています。特に直径5mm以下の微細なプラスチック粒子であるマイクロプラスチックは、生態系への深刻な影響が懸念されています。世界中のプラスチックごみが大きな潮の流れに乗って集積し、太平洋上には日本の面積の4倍以上、重量約7万9,000トンにも及ぶ「太平洋ゴミベルト」が形成されていることは、この問題の規模の大きさを物語っています。 - 乱獲と違法漁業:
世界の漁獲量の約2割が違法漁業によるものと推測され、世界の漁業資源の30%が過剰漁獲されているのが現状です。特にマグロやタラなど食物連鎖の上位に位置する資源ほど枯渇が指摘されています。過剰に捕獲された魚種が生物的に持続可能なレベルに戻るにはおおむね20年が必要とされており、このような乱獲は海洋生態系のバランスを崩すだけでなく、漁業に携わる人々の生活にも大きな影響を与えています。 - 海洋酸性化:
大気中の二酸化炭素濃度の上昇により、海水が酸性化する現象です。産業革命以前にはpH8.17程度であった海洋のpHは、現在約8.06程度にまで低下しており、多くの海洋生物はpH8を極端に下回る環境下で生存することが困難であるため、さらなる酸性化の進行は食い止められなければなりません。 - 気候変動の影響:
海水温の上昇や海面上昇は、海洋生態系に大きな変化をもたらし、サンゴの白化現象や海洋生物の生息域の変化を引き起こしています。海洋温暖化によってプランクトンが生息・増加しにくくなり、食物連鎖を通じて各種水産資源の減少に繋がることが危惧されています。
これらの課題は相互に関連しており、一つが解決されても他の問題が残るという複雑な構造を持っています。
SDGs目標14「海の豊かさを守ろう」が生まれた歴史的背景
SDGs目標14「海の豊かさを守ろう」が誕生した背景には、長年にわたる海洋環境問題への国際社会の認識の高まりがあります。1972年の国連人間環境会議(ストックホルム会議)以降、海洋汚染に関する国際的な議論が始まり、1982年には国連海洋法条約が採択され、海洋の利用と保護に関する国際的な枠組みが形成されました。
さらに海洋環境の劣化が地球規模で加速する中、2015年に採択されたSDGsにおいて、初めて独立した目標として「海の豊かさを守ろう」が設定されました。これは、海洋問題が地球全体の持続可能性にとって極めて重要であるという国際社会の強い意志の表れと言えます。
SDGs目標14「海の豊かさを守ろう」取り組み:世界と日本の具体的なアクション
SDGs目標14「海の豊かさを守ろう」のための取り組みは、国連、各国政府、地域社会、そして企業が一体となって進めるべき地球規模の課題です。ここでは、具体的な事例を通して、その多様な取り組みを紹介します。
SDGs目標14「海の豊かさを守ろう」:世界各国における取り組み事例
世界では、海洋保護のために様々なアプローチが取られています。
- 海洋保護区の設定:
多くの国で、生物多様性の保全や生態系の回復を目的とした海洋保護区(MPA)が設定されています。例えば、米国ではパパハナウモクアケア海洋国家記念物など広大な保護区が設けられています。 - プラスチック規制の強化:
欧州連合(EU)では、使い捨てプラスチック製品の使用を禁止する指令を導入し、プラスチックごみの削減に取り組んでいます。ケニアなど一部の国では、レジ袋の使用を厳しく制限しています。 - 国際協力による科学調査:
国連教育科学文化機関(UNESCO)の政府間海洋学委員会(IOC)などが中心となり、海洋酸性化や気候変動が海洋に与える影響に関する国際的な科学調査が進められています。
これらの取り組みは、各国がそれぞれの状況に応じて、海洋保護への貢献を目指していることを示しています。
SDGs目標14「海の豊かさを守ろう」:日本における取り組み事例
日本は四方を海に囲まれた海洋国家であり、古くから海の恵みと共に生きてきました。広大な排他的経済水域(EEZ)を有し、日本のEEZには全海洋生物種の14.6%が分布しており、生物多様性の「ホットスポット」であるとされています。そのため、SDGs目標14「海の豊かさを守ろう」のための取り組みにおいても、積極的な役割を担っています。
- 海洋基本計画:
日本政府は、海洋に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、海洋環境の保全、海洋資源の持続可能な利用、海洋科学技術の振興などが盛り込まれた海洋基本計画を策定しています。 - プラスチック資源循環戦略:
2019年に策定されたこの戦略では、プラスチックの3R(リデュース、リユース、リサイクル)に加え、再生材・バイオプラスチックの利用促進、海洋プラスチックごみ対策の強化などが掲げられています。 - ブルーカーボン生態系の保全・回復:
藻場や干潟といったブルーカーボン生態系は、二酸化炭素を吸収・貯留する能力が高く、気候変動対策としても注目されています。日本各地で、これらの生態系の保全や回復に向けた活動が行われています。 - 海洋生物多様性保全戦略:
2011年には環境省により「海洋生物多様性保全戦略」が策定され、海洋保護区の充実とネットワーク化、適切な海洋生物資源管理などが進められています。この戦略は、日本の重要課題である「社会インフラのグリーン化」や「地球規模問題への対応促進」の達成に資することを目指しています。 - 「里海」の維持支援:
古くから人間との関わりが深い沿岸海域である「里海」の維持支援も、日本の特徴的な取り組みです。これは、地域社会と海洋生態系の共存を目指すものです。
SDGs目標14「海の豊かさを守ろう」:国連における取り組み事例
国連は、世界の海洋問題を解決するための国際的な枠組みと協力体制を構築する上で中心的な役割を担っています。国連環境計画(UNEP)は、海洋や海域への世界の注意を向けさせる活動を積極的に進めてきました。
- 国連海洋法条約:
「海の憲法」とも呼ばれるこの条約は、海洋の利用と保護に関する包括的な国際法規を定めています。 - 国連総会決議:
国連総会は、毎年海洋と海洋法に関する決議を採択し、海洋保護の重要性を再確認し、各国に具体的な行動を促しています。 - 持続可能な開発のための国連海洋科学の10年:
2021年から2030年までの10年間は、「持続可能な開発のための国連海洋科学の10年」とされており、海洋科学の発展と応用を通じて、SDGs目標14の達成に貢献することを目指しています。
これらの国際的な枠組みは、各国が協力して海洋問題に取り組むための基盤となっています。また、違法・無報告・無規制(IUU)漁業対策のために、WWFなどの国際機関は、IUU漁業の抑制を目的とした寄港国措置協定(PSMA)の規制と管理強化の支援に取り組んでいます。
企業に求められるSDGs目標14「海の豊かさを守ろう」に向けた新たな視点
SDGs「海の豊かさを守ろう」取り組みにおいて、企業の役割は非常に重要です。単なるCSR(企業の社会的責任)活動としてではなく、持続可能なビジネスモデルを構築する上で不可欠な要素となっています。
サプライチェーン全体での環境負荷低減
企業は、自社の事業活動だけでなく、原材料の調達から製造、物流、販売、そして廃棄に至るサプライチェーン全体で環境負荷の低減に取り組む必要があります。特に、海洋プラスチック汚染の削減には、製品の設計段階からリサイクル性や生分解性を考慮することが求められます。
プラスチック問題への企業の貢献
プラスチック問題は、SDGs目標14「海の豊かさを守ろう」の達成における最大の課題の一つです。企業は、以下の方法で貢献できます。
- プラスチック使用量の削減: 製品の包装材や容器におけるプラスチック使用量を減らす。
- 代替素材への転換: 紙やバイオプラスチックなど、環境負荷の低い代替素材への切り替えを進める。
- リサイクルシステムの構築: 使用済みプラスチックの回収・リサイクルを促進する。
- リサイクル材の積極的な利用: 製品にリサイクルプラスチックを積極的に使用する。
SHIFT ONが提供する海の豊かさを守るためのソリューションをご紹介
国際紙パルプ商事株式会社が運営するSHIFT ONでは、企業の皆様のSDGs目標達成に向けた取り組みをサポートするソリューションを提供しています。
紙製人工芝:マイクロプラスチック問題への新たな解答
環境負荷の低いOJO⁺のペーパーターフ(紙製人工芝)は、従来のプラスチック製人工芝に代わる画期的な選択肢です。一般的な人工芝は、使用に伴いマイクロプラスチックが環境中に流出し、海洋汚染の一因となることが問題視されています。
しかし、OJO⁺のペーパーターフはマニラ麻を原料とした紙であるため、生分解性があり、マイクロプラスチックの発生を抑制し、海洋への負荷を大幅に低減します。
バイオプラスチック:持続可能な社会を築く素材革命
バイオプラスチックの導入は、石油由来プラスチックの使用量削減に大きく貢献します。バイオプラスチックは、植物などの再生可能なバイオマスを原料として製造されるため、化石資源への依存を減らし、温室効果ガス排出量の削減にも寄与します。環境負荷の低い素材への切り替えは、製品のライフサイクル全体での環境負荷を低減し、最終的に海洋に流れ出るプラスチックごみの量を減らすことにも繋がります。SHIFT ONでは、企業のニーズに合わせた様々な種類のバイオプラスチック素材を提供し、持続可能な製品開発を支援します。
バイオプラスチックの種類や選び方、そしてKPPが提供するバイオプラスチック製品を紹介します...サステナブルな環境対応樹脂素材と選び方を解説

脱プラ実現にバイオプラスチック
まとめ:SDGs目標14「海の豊かさを守ろう」に向けた取り組みは企業の新たな成長機会
SDGs「海の豊かさを守ろう」取り組みは、もはや単なる環境保護活動ではなく、企業にとって新たなビジネスチャンスと成長機会を生み出すものです。環境に配慮した製品開発、サプライチェーンの最適化、そして持続可能な資源の利用は、企業のブランド価値を高め、消費者からの信頼を獲得し、長期的な競争優位性を確立することにつながります。
SHIFT ONのソリューションは、企業の皆様が「海の豊かさを守る」というSDGs目標14に貢献しながら、同時にビジネスの持続可能性を高めるための具体的な手段を提供します。貴社のSDGsへの取り組みを加速させ、未来の世代に豊かな海を残すために、ぜひSHIFT ONにご相談ください。