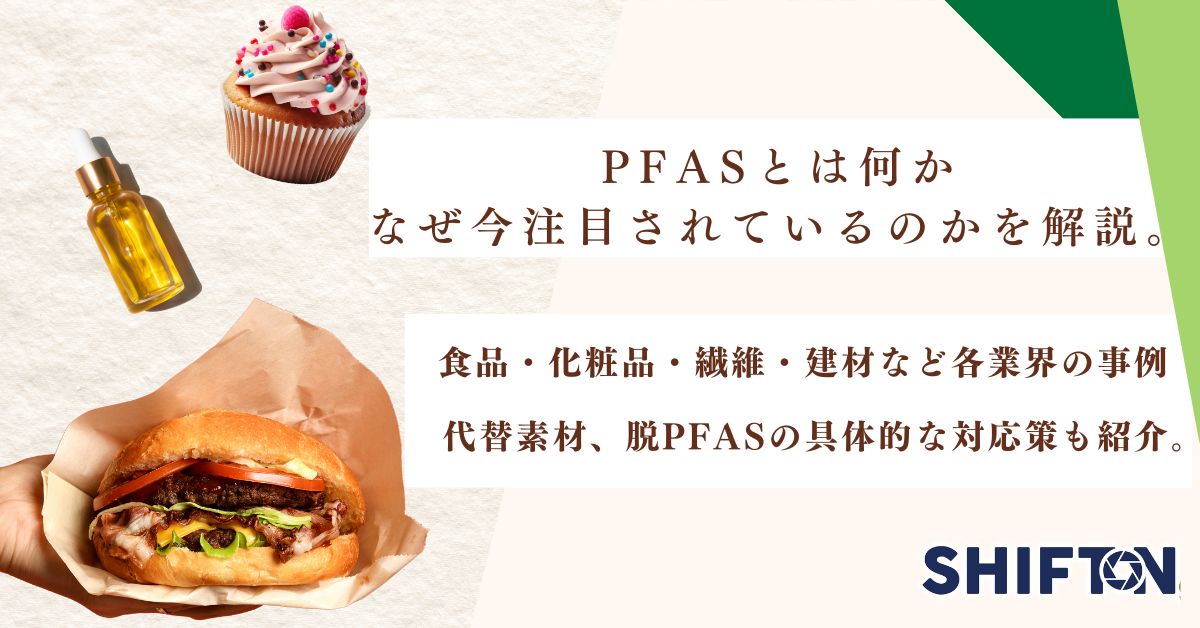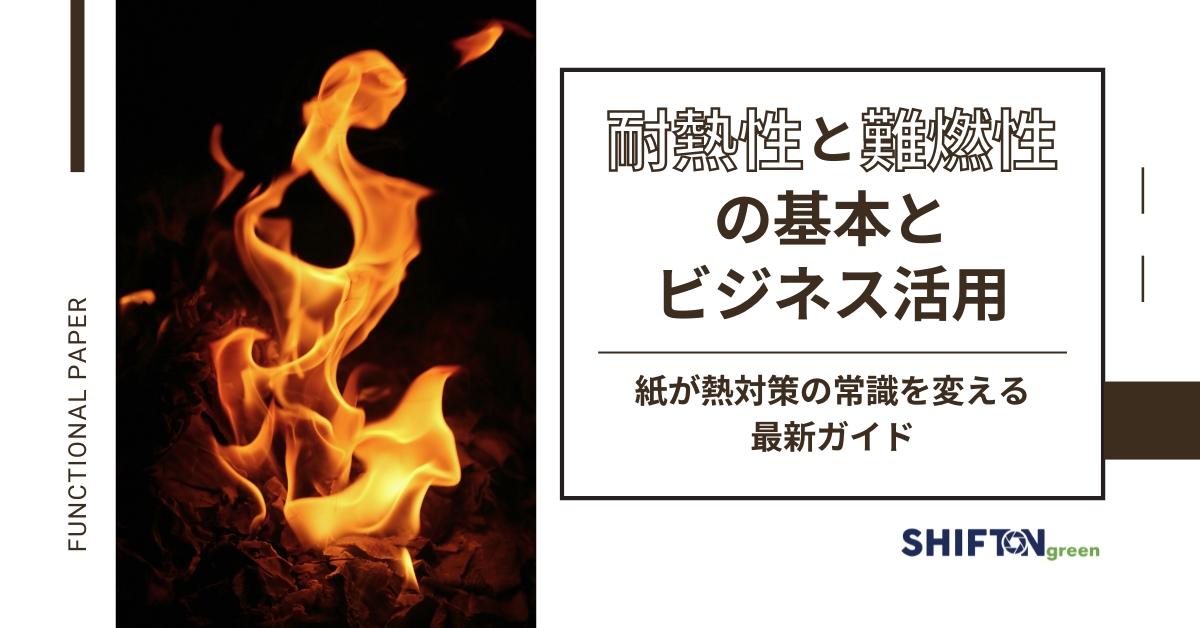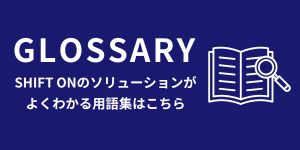荷崩れを防止して物流品質を守るには?原因と対策、有効な商材を解説

荷崩れとは、トラックなどで輸送中に積荷が崩れてしまう現象です。荷崩れが起きると商品の破損や配送遅延を招き、最悪の場合は荷物が車外へ落下して他車との衝突事故につながる危険性もあります。
実際、ある調査では輸送中の破損トラブル原因の第1位が「衝撃(ショック)」であり、荷崩れなどによる商品破損でクレームが発生すれば企業の信頼低下にも直結します。本記事では物流品質の指標や荷崩れ問題について解説し、主な原因と防止策、そしてSHIFT ONが提供する荷崩れ防止に役立つ商材をご紹介します。
物流品質とは何か

物流品質を支える主な要素:納期遵守・正確性・安全性
物流における品質とは、荷役作業や輸送といった物流サービスの正確性・安定性を示す指標です。具体的には、顧客と約束した日時を守る納期品質、品物や数量・配送先の誤りがない正確性品質、そして荷物を破損・汚損させず安全に届ける事故防止(商品品質)など複数の要素から成ります。
指定日時を守り、正しい商品を良好な状態で届けることが顧客満足に直結するため、物流現場ではこれらの品質維持が最重要視されます。品質が低下すれば荷主企業からの信頼を失い、納期遅延や欠品による顧客満足度低下で売上減少にも直結するリスクがあります。
PPMによる誤出荷率の定量管理
物流現場では、こうした誤配送・事故を防ぐためPPM(Parts Per Million)という単位でミス発生率を管理します。PPMは100万件あたりのミス件数を表す指標で、例えば100万件中3件の出荷ミスなら「3 PPM」となります。この値が小さいほど出荷精度が高いことを意味し、多くの物流企業がPPM最小化に努めています。
一般的な物流現場では50〜100PPM程度が目安とされ、最新の自動化倉庫でも完全ゼロにはできず5〜10PPM程度が限界といわれます。指標として見える化されたPPM値を継続的に改善していくことで、物流品質レベルの向上が図られます。
クレーム・事故件数のKPI化と「見える化」
物流品質では誤出荷率だけでなく、配送ミスや書類不備によるクレーム発生率や貨物事故率などもKPI(重要業績評価指標)として定量的に管理されます。例えばクレーム件数を総出荷件数で割り100万倍した値(PPM)で表せば、品質上の課題を客観的に測定可能です。こうした数値を用いて課題を“見える化”し、改善のPDCAを回すことで継続的な品質向上に繋げます。
国土交通省も2015年から物流事業者によるKPI導入を推進しており、多くの企業が競争力強化や持続可能な物流実現のために取り入れています。定量指標による共有でスタッフ全員が共通目標を認識し、組織全体で物流品質の底上げに取り組むことが重要です。
参考:国土交通省 物流事業者におけるKPI導入のあり方に関する検討会について
荷崩れとは:起こる原因とタイミング

荷崩れとは輸送中の振動や衝撃によって積荷がバランスを崩し、積み重ねた荷物が崩落してしまう現象です。トラック走行中は前述の通り常に上下・左右・前後方向に揺れが生じますが、その揺れの大きさは「地震の震度」に例えられるほどです。
例えば路面の段差や急ブレーキ時には震度4程度、時速50kmで半径100mのカーブを曲がるときは震度5相当、急発進や急ブレーキ時には震度7にも匹敵する激しい揺れが荷物に加わると言われています。つまり走行中は大小の“揺れの連続”に見舞われることが避けられず、この振動・衝撃に耐えられないと荷崩れが発生します。
また荷崩れは輸送中だけでなく、積み込み時や荷降ろし時など様々な場面で起こり得ます。実際の事故データでも、トラックへの積み込み作業中に荷が崩れて破損事故になるケースが全体の約2割を占めるとの報告があります。こうした荷崩れのリスクは輸送業者だけでなく荷主企業にも存在し、物流に携わるすべての立場で意識すべき問題です。
荷崩れの主な原因
荷崩れの原因はいくつかありますが、代表的なものは積み方・固定の不備と走行時の衝撃です。まず積載時の問題としては、過積載(トラックの許容量を超える荷物を載せる)や偏荷重(荷重が一部に偏っている)が挙げられます。重量バランスが悪いと荷台全体が不安定になり、振動で崩れやすくなります。
また荷物の上にさらに重い荷物を載せたり、荷物同士の間に隙間が空いた状態で積むことも危険です。走行中の揺れで荷物同士が動き、衝撃で崩れてしまうリスクが高まります。同様に、荷物の固定不足(ロープやバーで適切に固縛していない)も原因になります。荷物が荷台に固定されていないと、ブレーキやカーブ時の遠心力で荷全体が移動し積み崩れを起こします。さらに梱包の不備も見逃せません。
荷物自体が緩衝材なくむき出しだったり、段ボール箱が弱い状態だと、ちょっとした振動でも中身が壊れたり箱が潰れて全体が崩壊することがあります。緩衝材不足で荷物同士がぶつかれば損傷だけでなく、それが引き金となって積荷全体が崩れることもあります。このように、「積み方」「固定」「梱包」、そして「走行時の振動」の各要因が重なると荷崩れは発生しやすくなります。
荷崩れを防ぐための対策
荷崩れを事前に防止するには、「貨物の積み付け」「貨物の固縛」「運転方法」の3点を組み合わせて実行する必要があります。いくら丁寧に積み付けを行っても、走行中には常に震度4以上の揺れ・衝撃が加わると言われるため、積載だけでなく固縛や運転面も含めた総合的な対策が重要です。
荷崩れ防止の主要な取り組みとして以下3つを順に解説します
- 1運転方法の改善
- 2防振アイテムの活用
- 3固縛アイテムの活用
(1) 運転方法の改善による衝撃低減
輸送中の振動・衝撃をゼロにすることはできませんが、慎重な運転によってその影響を可能な限り抑えることができます。ポイントは“急”の付く操作をしないことです。急発進・急ブレーキ・急ハンドルなど唐突な操作は荷崩れの大きな原因になるため厳禁です。カーブではスピードを落として丁寧に走行し、前の車との車間距離に十分余裕を持って走ることで、急ブレーキの発生自体を防ぎます。
日頃から過積載や偏荷重を避ける積み方を徹底し、荷物に過度な負荷がかからない運行計画と安全運転を心掛けましょう。トラックドライバーだけでなく、運行管理者や荷主も協力して安全運転教育や衝撃データの活用(ドライブレコーダや衝撃計測器で急ブレーキの可視化する等)を行えば、現場全体で荷崩れ防止意識を高める効果が期待できます。
(2) 防振アイテムの活用による振動対策
荷台の振動そのものを和らげるには、防振対策用の資材を活用する方法があります。例えば荷物を載せる台座として防振パレット(振動吸収機能を持つ特殊パレット)を使用すれば、路面からの振動を大幅に緩和できます。また荷物と荷物の間や荷物と床面の間に防振クッションや衝撃吸収パッドを挟むことで、走行中の細かな揺れによる荷物への衝撃を減らす効果があります。
特に精密機器や美術品など振動に弱い貨物には、防振パレット・防振台といった専用アイテムの導入が有効です。さらに、輸送中に所定以上の衝撃が加わったことを色の変化で検知する衝撃検知ラベル(ショックウォッチ)を貼付するのも間接的な対策になります。ショックウォッチは荷物に貼るだけで作業者への抑止力となり、万一強い衝撃が加わると赤く変色して衝撃の有無をひと目で確認できます。
衝撃の“見える化”により荷扱い担当者へ注意喚起することで、荷物の取り扱いをより慎重にさせる効果が期待できます。このように防振グッズを適材適所で活用し、貨物に伝わる振動そのものを減衰させることも荷崩れ防止の重要なポイントです。
(3) 固縛アイテムの活用による荷物固定
積み込んだ荷物は固縛(しっかり固定)して初めて安全に運べます。まず基本はロープやベルトによる荷締めです。荷台の前後左右に荷物との隙間がある場合、木材のストッパー(止め木)を入れて荷ずれを防止し、ロープやワイヤーで荷物を動かないよう縛ります。特に長尺物を積む際は、最低でも前後と中央の3箇所以上を固定するのが望ましいです。
平ボディ車でシート(帆布)を被せる場合も、シートを掛けただけでは固定効果が不十分なため、その上から必ずロープやバンドで縛りましょう。近年はワンタッチで締め付けできるラッシングベルト(荷締めベルト)やラチェット式の荷崩れ防止ベルト(通称「ガッチャ」)が普及しており、誰でも確実に強いテンションで荷物を固定できます。荷物同士や荷物と荷台との間に滑り止めマットやゴムシートを敷くことも効果的です。
これによりブレーキ時の荷物の横滑りを防ぎ、ロープ固定だけでは防ぎきれない細かなズレを抑制できます。角張った荷物にはコーナー緩衝材(角当て板)を当ててバンドの締め付け圧で箱が潰れるのを防ぐとともに、荷物全体を一体化させるのも有効です。紙製のL字補強材「エッジボード」を荷物の四隅にあてがい、その上からバンドやフィルムで荷物ごと締め上げれば、角の保護と荷崩れ防止が同時に図れます。
エッジボードは板紙を積層プレスして作られており強度は木材並みで、荷崩れ防止やPPバンドの食い込み防止、角部の破損防止に最適な資材です。使い終わればリサイクル可能な環境配慮製品でもあり、簡単ながら荷崩れ防止に高い効果を発揮します。
荷崩れ対策が必要な理由

荷崩れが企業信用に及ぼす悪影響
輸送中の荷崩れで製品が破損し顧客クレームに発展すれば、取引先からの信頼が損なわれかねません。物流品質が低下すると荷主からの評価も下がり、企業にとって荷崩れ防止は重要課題となります。破損トラブルが頻発すれば商品の価値やブランドイメージも低下し、最悪の場合は取引継続に影響する恐れもあります。
実際、物流における誤出荷や破損などのミスが多発するとそれだけ信頼を失い、リカバリー対応コストも増大するとの指摘があります。荷崩れによるクレーム一件一件が企業イメージを損なうリスクだと認識し、防止に努める必要があります。
荷崩れが招く労災・交通事故リスク
荷崩れは現場作業や輸送中の安全面にも大きなリスクです。例えば積み込み作業中に荷が崩れて作業員に落下すれば重傷事故につながりますし、走行中に荷物が崩れて道路へ落下すれば他車への衝突事故を引き起こす可能性があります。
実際、トラックドライバーの死傷事故は「運転中」よりも荷役作業中のほうが圧倒的に多い実態があります。2020年の貨物運送事業における死傷事故1万5,508件のうち約7割が荷役作業時に発生し、内訳は「墜落・転落」が27%と最も多く、「荷の固定・固縛不良による荷崩れ等の事故」も約10%報告されています。毎年のように荷崩れによる労働災害や交通事故が報告されており、安全管理上も荷崩れ対策は避けて通れません。
参照: 2020年(令和2年)確定値 | 陸上貨物運送事業労働災害防止協会(陸災防)
積付け・固縛不良が事故原因の主要な一因
国土交通省の分析によれば、国内の貨物事故要因のうち約3~4割は積み付け不良や固縛不良など適切な荷扱いが行われなかったことに起因しているとされます。つまり荷崩れ対策を怠ったために防げたはずの事故が相当数発生しているのです。裏を返せば、正しい積載・固定を徹底すれば防げる事故が多いということであり、現場での荷崩れ対策徹底が物流安全向上のカギとなります。
実際、荷台での荷物固定作業中に起きる転落事故や、走行中の急ブレーキ時に固定不足の荷が前方に崩れる事故など、積み方・締め方の不備が大きな事故に直結するケースが少なくありません。ヒヤリハット段階から積付け方法を見直し、荷崩れゼロを目指す取り組みが必要です。
参照:日本海事検定協会 輸送貨物の事故情報に関するデータベース報告書
振動が誘発する荷崩れ現象と対策の重要性
トラック走行中は路面の凹凸や加減速・カーブに伴い、上下・前後・左右あらゆる方向の振動衝撃が連続的に積荷に加わります。特に上下方向の振動は荷と荷台・荷同士の摩擦を大きく低下させ、静止時に比べ荷崩れが格段に起きやすい状態になります。いわば走行中の積荷は常に小さな地震に晒されているようなものであり、その振動環境下で生じる荷崩れを防ぐ対策は不可欠です。
例えば路面の段差や強めのブレーキでは震度4程度、速度50km/hで半径100mのカーブを曲がるときは震度5相当、急発進や急ブレーキ時には震度7にも匹敵する強い揺れが荷物に加わるとも言われています。
実際、トラック走行中には大小の“揺れ”が連続して押し寄せてくるため、積荷への影響を考えると「いつも震度4以上の地震に襲われている」状態にあります。この振動・衝撃に耐えられなければ荷崩れが発生するため、適切な固定器具の使用や緩衝材によるすき間充填などの対策を講じ、安全な輸送環境を整えることが求められます。
SHIFT ONの荷崩れ防止商材:物流現場を支える製品紹介

ここではKPPが取り扱う荷崩れ防止に役立つ主な商材として、梱包用フィルムからパレット上の固定具、大型の繰り返し使える輸送容器まで3種類をご紹介します。これらを活用することで荷崩れ防止はもちろん、作業効率や環境配慮にも貢献できます
1. ストレッチフィルム(荷崩れ防止用ラップ)
ストレッチフィルムとは、パレットなどに積み上げた荷物をぐるぐる巻きに包み込み、一体化させて固定するための梱包用フィルムです。柔軟で強度のあるポリエチレン製フィルムを引っ張り伸ばしながら荷物全体に巻き付けることで、巻き終わった後にフィルムが収縮して荷物をぴったり締め付け、輸送中の荷崩れを防止します。
ストレッチフィルムで荷物全体を包めばホコリや雨水による汚損も防げるため、防塵・防湿効果も高い梱包材です。実際、ストレッチフィルムは梱包した商品のほこりや湿気からの保護に優れ、製品品質の長期間維持に役立つとされています。
KPPでは手巻き用・機械巻き用から軽量物用・重量物用まで様々な厚み・サイズのストレッチフィルムを取り扱っており、荷物の大きさや重量に応じた適切なフィルム選定が可能です。フィルムによる梱包は簡便かつ低コストで実施でき、多品種少量出荷から一括パレット輸送まで幅広く対応できる荷崩れ防止策と言えるでしょう。
2. 平板アングル(紙製エッジボード)
平板アングルは紙でできたL字型の補強材で、荷物の角に当ててバンドやベルトと併用することで荷物を締め付け固定するための資材です。段ボール板を何層にも重ね圧縮して作られており木材にも匹敵する強度を持つため、重量物を含むパレット積み貨物の角当て(コーナー補強)として広く利用されています。
使い方はシンプルで、荷物の四隅に平板アングルをあてがい、その上からPPバンドやストレッチフィルムで荷物ごと締め上げます。こうすることで荷物の角からの崩れを防ぐと同時に、バンドの締め付けによる箱潰れも防止できます。平板アングルを巻いた荷物は角が保護され安定性が増すため、トラックでの急ブレーキやカーブでも崩れにくくなります。
実際、紙製L型アングル材であるエッジボードは荷崩れや角の破損を防ぐ保護具として世界40ヶ国以上で使用されており、輸送中だけでなく地震時の保管製品の荷崩れ防止や結束バンドの食い込み防止、段積み時の補強など用途も多岐にわたります。また紙製品なので使用後はリサイクル可能で環境にも優しい点も特長です。
KPPの物流総合カタログではサイズ・厚みなど用途に応じた各種エッジボード製品が紹介されており、荷物の大きさや重量に合わせた角当て材を選ぶことができます。低コストで導入しやすい平板アングルは、簡単ながら荷崩れ防止に高い効果を発揮する頼もしい梱包資材です。
3. スリーブボックス(折り畳み式大型ボックス)【ピタフィット】

スリーブボックスはパレットの上に被せて使用する大型の箱型コンテナで、四方の側面(スリーブ)と上下の板(天板・底板)で構成される繰り返し使える輸送容器です。樹脂製パネルとプラスチックパレットを組み合わせており、使わない時はスリーブ部分を折り畳んでコンパクトにできる設計です。スリーブボックスに荷物を収めて蓋をすれば、トラック輸送中に荷物が飛び出したり崩れたりする心配はほぼなくなります。
KPPが取り扱う新商品「ピタフィット」は岐阜プラスチック工業(株)製の最新スリーブボックスで、組み立てが容易で様々なパレットサイズに対応可能な汎用コンテナです。実際にピタフィットを飲料の長距離輸送へ導入した事例では、空間効率の向上によってトラック台数を半減し輸送コストを50%削減できたとの報告もあります。
使用後に折り畳んで回収・再利用する運用は必要ですが、それを考慮してもトータルコスト削減と廃プラごみ削減に大きな効果を発揮する画期的な容器と言えるでしょう。ピタフィットの製品詳細や導入事例については以下の紹介記事もご参照ください。
現場の声として要望が強かったのが、2段積みの作業性です。...輸送効率2倍!

「ピタフィット」のご紹介
物流品質向上へ、荷崩れ防止に今すぐ取り組もう
本記事では荷崩れの原因と対策、そして防止に役立つ製品について解説しました。荷崩れを防ぐことは、お預かりした大切な荷物を守ることはもちろん、周囲を走る車両の安全にも直結する重要課題です。荷主・運送事業者の双方が協力し、積付け方法の改善や適切な固定、安全運転の徹底を図ることで、物流現場の品質水準は確実に向上します。
KPPでは荷崩れ対策を含む物流品質向上ソリューションを多数取り扱っており、本記事で紹介した以外にもRanpak社の「紙緩衝材ソリューション」(エコで効率的な緩衝材)や高機能パレットなど様々な製品・サービスをご提供可能です。
製品の詳細や導入相談については、ぜひ資料ダウンロードやお問い合わせをご活用ください。物流総合カタログでは荷崩れ防止を含む包装資材・物流機器のラインナップをご覧いただけます。荷崩れ防止への一歩が、物流品質と安全性の飛躍的な向上につながるはずです。