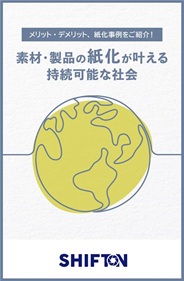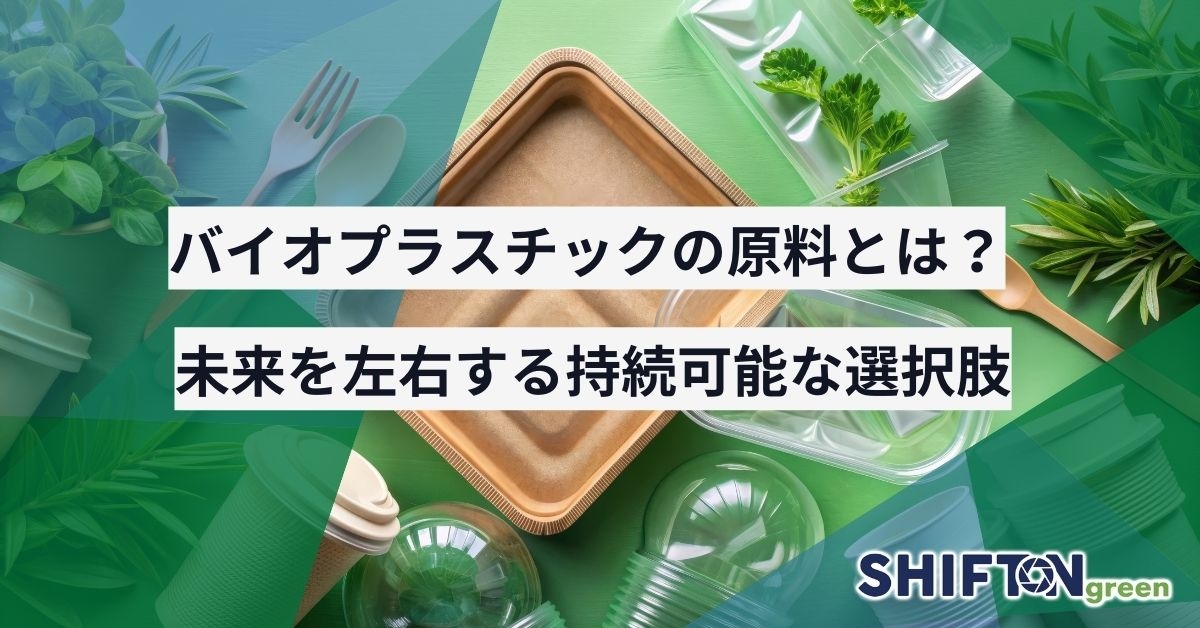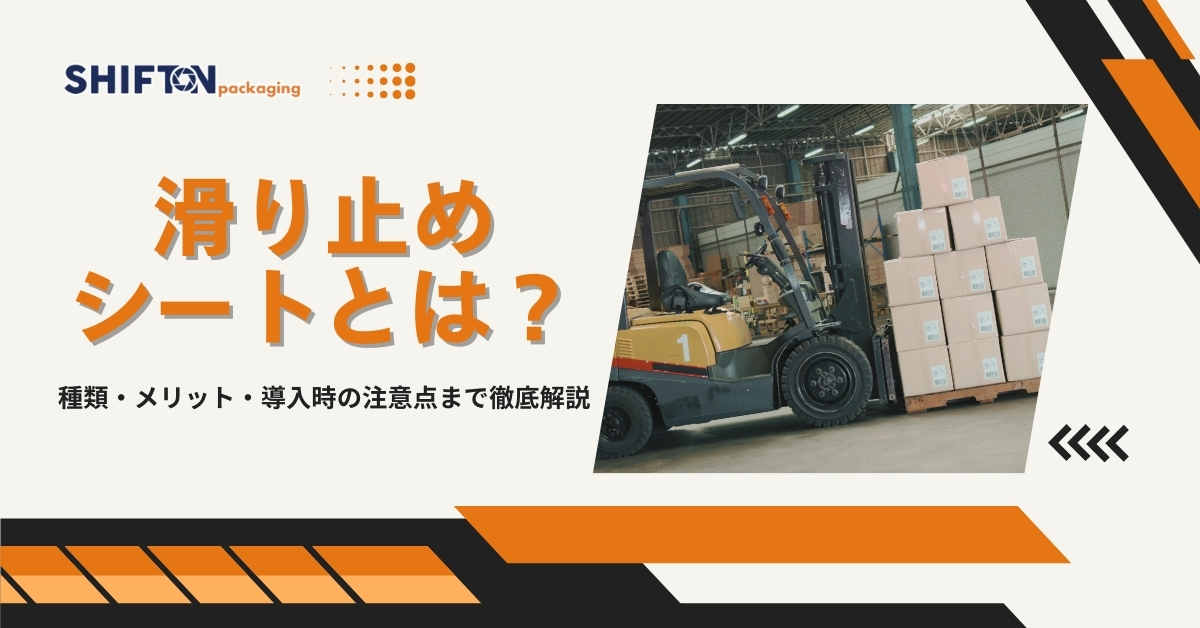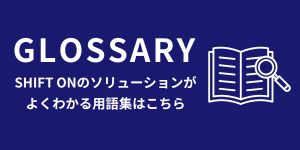紙化できる製品事例をご紹介 | プラスチック製品から紙製品へ
最終更新日:2025/10/27

個人・企業問わずに環境問題への関心が高まったことにより、プラスチックの代替製品の使用例が増えています。
なかでも自然界で生分解が可能であり、長年使用されてきた素材・紙に注目が集まっています。
今回は使用する素材をプラスチックから紙に変更する「紙化」の目的とメリットを、紙化対応した製品例、活用事例などからご説明します。
なぜプラスチックを紙化するのか?紙とプラスチックの違いを解説
使用する素材をプラスチックから紙に変える「紙化」で実現できることとして、以下のようなことが挙げられます。
- 石油資源の使用量・廃棄量が削減できる
- 使用済のプラスチックを焼却する際に発生する、温室効果ガスの抑制
- 生分解を有する場合、比較的短時間でCO2と水に分解されるため、環境中に残留するプラスチックごみの削減につながる
- 環境中で分解されるため、廃棄物処理の手間やコストが削減される
参照:環境省 プラスチック資源循環
バイオプラスチックのメリット
わかりやすい用語解説:バイオプラスチックとは?
紙化の目的として、一度しか使用されない品の廃棄処理における負担を減らすというものがあります。
そのために微生物などの作用により生分解が可能な性質を有していること、化石燃料を使用していないことで焼却しても温室効果ガスの発生が抑えられることから、紙の使用がおこなわれています。
プラスチックは安価で機能性が高く、大量生産できることから多くの製品に使用されてきました。
2021年には約1,045万トンのプラスチック樹脂が生産され、約824万トンのプラスチックが廃棄されています。
有効利用されている廃棄物のうち、62%はサーマルリサイクル(焼却処理をおこなう際に発生するエネルギーを回収)です。
今後の課題として単純焼却・埋め立てにまわっている廃棄物をリサイクルとして有効利用する割合を増やすこと、マテリアルリサイクル(再生利用)率を増やすことが挙げられます。
現状、モノからモノに再利用をおこなうマテリアルリサイクルは21%です。これには分別の手間がかかること、リサイクルコストが大きいこと、品質が劣化することなどのデメリットが存在します。
参照:一般社団法人プラスチック循環利用協会
2022年12月掲載 2021年廃プラスチック総排出量は824万t、有効利用率は87% プラスチック製品の生産・廃棄・再資源化・処理処分の状況(マテリアルフロー図)を公表
一方、紙・板紙の2021年における生産量は約2393万トン、うち古紙回収量は約1846万トンであり約79%という高い回収率が保たれています。
ただ、ワンウェイでの使用により再び資源としては利用できない紙や機能を付随された機能紙が存在するため、回収には限界があります。
そのなかでも古紙利用率は1970年当初の34%から2021年には67%まで大きく成長しています。このことから、日本では使用済み紙・板紙の回収、リサイクルスキームは確立されているといえます。
参照:公益財団法人古紙再生促進センター
数字で見る古紙再生
日本の紙リサイクル
高い耐久性、加工性を持つことからプラスチックが使用できる場面は多くあります。しかし回収から再利用までを考えると、シングルユース(1度しか使用しない、すぐ捨てる)製品を紙化することは合理的と言えます。
参照:日本製紙連合会 製紙産業の現状
紙・板紙
参照:環境省
印刷用紙に係る古紙の需給動向
紙化の背景にある3つの環境問題
環境問題は大きな3つの軸に分けられます。
地球温暖化・海洋プラスチックによる汚染・限りある資源の枯渇です。
地球温暖化
温室効果ガスは太陽から地球に降り注ぐ光によって暖められた熱を吸収する性質をもっているため、地球の平均温度は約15℃と、生物が生息できる温度を保っています。
しかし近年では産業活動の活発化などにより温室効果ガスが大量に排出され、大気中の濃度が高まり、熱の吸収が増加しています。吸収の増加に伴い地上の温度が上昇する地球温暖化に繋がっています。
参照:環境省 【平成9年版環境白書】
第1節 2 地球温暖化のメカニズム
参照:環境省 全国地球温暖化防止活動推進センター
温暖化とは?
気温の上昇は様々な変動をもたらします。 今回はなぜ脱炭素が重要で、どんなことに取り組めばいいのかを解説していきます。 ...
氷河の融解による海面水位の上昇、陸および海の生態系への影響、生物全体における健康への影響が考えられます。
温室効果ガスが引き起こす事象についての詳細はこちらの記事をご覧ください。
温室効果ガスが引き起こす事象の詳細はこちら

シリーズ脱炭素社会 | 脱炭素社会のための取り組み
海洋へ流出したプラスチックごみ
適切な廃棄処分がおこなわれず、環境内に流出したプラスチックはやがて海に流れ着き、摩擦などで微細なマイクロプラスチックへと変化します。
現時点における世界の海に漂う廃棄プラスチックの量は約1億5,000万トンとされており、さらに年間800万トンが新たに流出していると考えられています。
参照:WWFジャパン
海洋プラスチック問題について
流出したプラスチックやマイクロプラスチックが与える影響についてはこちらの記事をご覧ください。 日本近辺の海に漂流しているごみ、北極や南極までも漂着しているごみの多くがプラスチック製であると言われています。...
マイクロプラスチックが与える影響を紐解く

マイクロプラスチックって何?
環境と生態に与える影響をひも解いていく
限りある資源の枯渇
多くのプラスチックは、石油を生成して得られるナフサという油を原料にして作られています。
世界の石油確認埋蔵量は、2020年末時点で1兆7,324億バレルであり、これを2020年の石油生産量で除した可採年数は53.5年となりました。
可採埋蔵量は地中の探査により増加する可能性があるため、数値は一定ではありませんが、枯渇するときは必ず訪れます。
また、日本ではほとんど石油が取れないため、入手のほとんどを輸入に頼っています。石油の価格は世界情勢によって変動し、ここ数年は上昇傾向にあります。原料の値段があがれば、製品であるプラスチックの値段も上がっています。
参照:一般社団法人プラスチック循環利用協会 プラスチックのはてな
プラスチックの原料「ナフサ」ってなに?わかりやすく解説します!
参照:経済産業省資源エネルギー庁 令和3年度エネルギーに関する年次報告(エネルギー白書2022)
一次エネルギーの動向
参照:経済産業省資源エネルギー庁
カーボンニュートラルで環境にやさしいプラスチックを目指して
プラスチックを紙に代替する紙化のメリット
紙化することで得られるメリットは以下の3つです。
環境対応
紙の原材料は木材であり、パルプの生成から抄紙加工がおこなわれます。
生産過程ではプラスチックと比べ、消費するエネルギーが少ないことが挙げられます。
さらに木は成長過程でCO2を吸収すること、焼却時に発生するCO2が少ないこと、万が一廃棄されずとも自然環境下で生分解されることから環境負担が少ない素材です。さらに古紙となってリサイクルが可能です。
さらなるリサイクルの仕組みとして、クローズドリサイクルが挙げられます。
弊社では実績として、段ボールの原紙・製品供給(動脈)と古紙回収(静脈)を一元管理し、回収した古紙を原料化し、再度製品化した段ボールをお客様ご利用いただく取り組みを実施しています。
このシステムにより、自社内での資源循環のリサイクルループの実現、使用から回収までの見える化が可能です。
クローズドリサイクルについての詳細についてはこちらの記事をご覧ください。 お客様から排出された廃棄物を、再度お客様が使用する製品に戻し再納入する、クローズドリサイクルとしておこなっています。...
クローズドリサイクルについての詳細はこちら
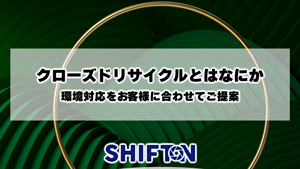
クローズドリサイクルとはなにか | 環境対応をお客様に合わせてご提案
そして紙化の価値は、上記に挙げた環境対応という“善意”だけにとどまらず、企業の競争力を高める実戦的な手段へと進化しています。ブランドの差別化からマーケティング効果、生産効率の向上などの利点もあります。
以下では、紙化が企業にもたらす“成果としてのメリット”を具体的に解説します。
ブランド差別化やマーケティング効果
プラスチック包装を紙に変更することは、企業の環境への取り組みを体現するわかりやすいアクションとなり、企業イメージ向上につながりやすいのです。
環境問題への積極的な対応は消費者や投資家から評価され、信頼獲得やブランド価値の向上に寄与します。
実際にネスレ日本では菓子「キットカット」の外袋を紙包装に切り替えた際、「紙に変わったんだ」といった好意的な反応が購入者から多数寄せられました。
このようなポジティブな消費者の声はブランド差別化に直結し、結果として企業のマーケティング効果を高めます。
さらに、環境に配慮した紙包装への変更そのものがニュース性を帯び、プレスリリースやSNSで話題になるケースもあります。
紙化の取り組みは単なる包材変更に留まらず、「エコな企業」というブランドメッセージを発信するマーケティング施策とも言えます。
デジタル広告が埋もれがちな現代において、実際の製品パッケージを通じて訴求することで消費者の印象に強く残るため中長期的な競合優位性を築きやすいのも利点でしょう。
機能性と加工自由度
紙素材は厚みや質感を調整することで様々な製品に対応できる汎用性を持ちます。
ストローや容器、段ボールなど用途に応じて薄紙から厚紙まで選択でき、必要な強度や形状を実現可能です。
また印刷適性が高く、自由な形状に成形しやすいのも特長で、軽量であるため輸送効率も良好です。
プラスチックに比べ紙は素材自体にコシがあり折り曲げやすいため、複雑な折り構造や微細な表現も行いやすく、デザインの幅が広がります。
紙化によってオリジナル性の高いパッケージデザインも実現できます。
例えばネスレ日本は「キットカット」の外袋を紙製に変更した際、包装に折り鶴の作り方を印刷し、食べ終えたパッケージで折り紙を楽しめる仕掛けを施しました。
紙パッケージだからこそ可能になったこの折り紙コミュニケーションは日本伝統の願いを伝える象徴を取り入れたもので、消費者が実際にメッセージを書いて折り鶴を作るという新しい体験を生み出しました。
このように紙ならではの柔軟な加工性を活かせば、パッケージ自体が商品の付加価値や話題性を高めるツールとなり得るのです。
プラスチックを紙に代替する際に懸念されるポイント・デメリット
もちろん紙化には課題も存在します。
ここでは紙への置き換えにおいて懸念されるポイントとして挙げられる3点について解説します。
機能性、品質の担保
紙素材はプラスチックと比べて強度や耐久性の面で劣る場合があります。
重量物を入れると破れる可能性があり、衝撃にも弱く、長期間の保存で劣化しやすい点は無視できません。
また、耐水・耐湿性の低さにも注意が必要です。
紙は水分を吸収すると膨張・軟化して強度が低下しやすいため、湿度の高い環境や液体・油分と直接接触する用途には不向きです。
実際、密封性や耐熱性が強く求められる製品では紙化が難しく、食品や化粧品など内容物を湿気や液体から守る必要がある包装には適さない場合があります。
これら機能面のハンデを克服するために、紙にコーティング加工を施して防水・耐油性を高めたり、複数の紙層を重ねて強度を補強したりするといった工夫が行われています。
しかし、防水性向上のためのラミネート加工などを施すと紙包装であってもプラスチックフィルムとの複合素材となり、せっかくのリサイクル容易性が低下するジレンマも指摘されています。
また、特殊加工を重ねればその分製造コストが増大し、場合によっては従来のプラスチック包装より高価になってしまうこともあり得ます。
紙化にあたっては、こうした品質・機能上の課題とコスト増とのバランスを見極めることが重要です。
「脱炭素とはなにか」や「個人や企業がおこなう取り組み」などを解説しました。 ...紙化とはなにか、詳細な事例はこちら

シリーズ脱炭素社会|脱プラスチックと紙化を解説
素材の安定供給
紙への需要が急増した場合の原材料の安定供給も懸念事項です。
紙の原料であるパルプは木材から得られますが、世界的な紙需要の高まりは森林資源への負荷を強めるリスクがあります。
実際、紙パルプの製造には大量の水資源や森林資源が必要であり、需要の急増は森林伐採の加速や生態系破壊につながる恐れが指摘されています。
違法伐採の誘発や、生物多様性への影響も無視できません。
このため紙化を進める企業には、FSC認証木材など適切に管理された森林資源から原料を調達することや、古紙リサイクルの活用を推進することが求められます。
日本は古紙回収率が約80%と高水準で推移していますが、食品包装など衛生面でリサイクル材の利用に制約がある分野もあり、用途によっては十分な再生原料を確保できない可能性もあります。
紙化の検討にあたっては、こうした原材料サプライチェーンの持続可能性と安定調達に対する配慮が欠かせません。
FSC®認証は、適切に管理された森林と、責任もって調達された林産物に対する国際的な認証制度...関連記事はこちら

FSC®認証とは?活用メリットと企業の使用事例などをご紹介
製造工程の簡略化
最後に、紙化による製造工程への影響も課題となります。
現在プラスチック包装で確立されている生産ラインを紙対応に切り替えるには、新たな機械設備の導入や金型の変更、接着・折り加工など工程の追加が必要になることがあります。
例えば、従来プラスチック容器を成型充填していたラインでは、紙製パッケージ用に包装形態や充填方法を見直さねばならず、そのための初期投資や技術検証が必要です。
また、紙包装材はプラスチックフィルムに比べかさばりやすく、在庫保管や輸送時の効率が下がる傾向も指摘されています。
このような工程面の課題に対応するには、社内外の関係部門を巻き込んだ綿密な調整と計画が求められます。
実際ネスレ日本の事例でも、紙化プロジェクトにはマーケティング・包装開発・調達・生産現場まで含めた社内横断のチーム体制で臨み、立ち上げから製品発売まで約1年を要しています。
紙化を円滑に進めるには、このように製造プロセス全体を見据えた上で工程をシンプルかつ効率的に再構築する工夫が必要となるでしょう。
環境にやさしい包装紙への転換:紙化対応できる製品例
何層にも紙を重ねたり、圧縮して密度を高めたりすることで耐久性や耐水性を強化した製品が存在します。
紙化対応できる製品例を、以下の3つに分けてご紹介します。
配送・梱包資材
配送・梱包資材では、以下での紙化対応が可能です。
- ガムテープ
- パルプモールド
- 緩衝材
- 紙製うち袋
一般的にガムテープといえば、クラフト紙や布・OPPなどの基材にゴム・樹脂系の粘着剤を塗布して製造されている粘着テープを思い浮かべる方が多いですが、本来ガムテープとは、クラフト紙の片面に水溶性の糊が塗布されている、剥離剤や合成樹脂系接着剤の使用のない、水で粘着性を生むテープのことを指します。
弊社で取り扱うリカテープは、段ボールに貼られていてもそのままリサイクルが可能であり、廃棄する際にはがす手間がかかりません。
リカテープについてはこちらの記事にて詳しくご紹介しています。 商品の梱包や配送時に封として使用される梱包用テープには、紙素材で出来たクラフトテープや目に沿って手で切れる布製テープ・OPPテープのほかに...
リカテープとはなにか、詳細な説明はこちら

段ボールと一緒にリサイクルできるリカテープとは?
機能性の高いテープを使用するお客様の声もご紹介
パルプモールドは古紙を中心とした植物繊維を水で溶かし、成形する体紙成形品で、緩衝材などに使用されています。
製造の過程で糊や接着材を使用せず、さまざまな古紙を原料とできるため、自然環境への負担が少なく、使用後の焼却時にも有害物質が発生しません。
製品の特長としてクッション性があり、成形自由度が高いことから、卵パックや果実トレーのほかにも、家電や工業用品の緩衝材にも使用されています。
ほかにも紙緩衝材としてRanpakが挙げられます。 物流業務に関わる工程を高度化・仕組化することで業務の流れが一本化し、戦略的な物流管理や出荷効率向上につながります...
Ranpakでの課題解決実例もご紹介しています。詳細はこちらの記事をご覧ください。
Ranpakでの課題解決事例はこちら

紙緩衝材を使用したロジスティクス |
物流業務の効率化によって生まれる利益をご紹介
製品の梱包に紙製うち袋の使用を推奨いたします。
フェイスカバーにも使用されている素材であることから通気性がよく、サイズ展開も多様です。
石油由来素材から紙素材へ切り替えるための資料もDLできる記事はこちらよりご覧ください。 従来のフェイスカバーなどが問題視される中、紙製の脱プラツールが持つ環境に優しい特性を、今回は詳しくご紹介したいと思います。...
石油由来素材から紙素材への詳細資料はこちら

紙製のフェイスカバーで洋服試着をサステナブルでもっと快適に!
製品の包装パッケージ
製品の包装パッケージでは、以下での紙化対応が可能です。
- 食品の二次・三次包装、外箱
- ペットフード包装
- 日用雑貨
- 衣類
- DM封筒
プラスチック使用量削減につながることはもちろん、印刷が容易なこと、変形が簡単なこと、軽さがあることが特徴です。
ダイレクトメールとして届く広告の封筒を紙製に変更した事例があります。
フルカラーや写真などの印刷適正があるため、プラスチック製の封筒に比べ視認性が向上し、訴求力のある広告が可能となります。
広告効果向上と環境対応を両立した取り組み例についてはこちらの記事をご覧ください。 今回は紙封筒製造までの過程や、紙封筒ならではできることを中心にお話を伺いました。...
広告効果向上と環境対応の両立事例はこちら

DMでの広告効果向上と環境対応の両立|
株式会社アド・ダイセンでの環境対応事例を紐解く
食品容器包装
食品に直接触れる容器・包装や資材の分野では、以下での紙化対応が可能です。
- 弁当などの容器
- ストローなどカトラリー
- 飲料コップ
特殊な加工を施すことで、耐水・耐油性を有し、食品に包装紙の臭い移りがないことから、直接食品に触れる容器一次包装にも使用されています。
使い捨てのイメージがあった紙コップは、資源として回収することで再利用が可能となります。
弊社では2022年8月から9月にかけてサッカーJ2リーグ所属のザスパクサツと連帯し、正田醬油スタジアムにおいて使用済み紙コップを回収し、これらを原料としたトイレットペーパーを製造・再利用するという取り組みを実施いたしました。
まとめ
紙化の目的は、使用した資材を一度きりで終わらせないこと。
たとえ繰り返し使用できない場合でも、できる限り環境負荷の少ない素材を選ぶことにあります。
プラスチックと紙、それぞれの特性を踏まえて最適な素材を選定することで、限りある資源の枯渇を防ぎ、持続可能な社会づくりに貢献することが可能です。
紙化のメリット・デメリットを整理し、実際の導入事例を多数掲載した資料をご用意しました。
紙といっても用途に応じて最適な紙種・仕様はさまざま。
当社では、豊富な紙種と加工技術をもとに、用途やご予算に合わせた柔軟な提案が可能です。
また、本文で紹介した懸念点(機能性・供給・工程・コスト)についても、お客様が最も重視するポイントに応じた最適解を事例とともに解説。
記事では紹介しきれなかった未掲載事例も多数収録しています。
意思決定の比較検討に、ぜひご活用ください。
詳しくお問い合わせご希望の方はこちら
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。